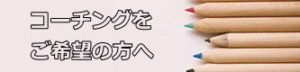「マルセル・フグがいない」
1月30日に発表された東京マラソン2024(3月3日開催)車いすマラソン男子の招待選手の資料を見て、こう思ったのは、毎年このマラソンを取材している私だけではないだろう。
マルセル・フグ(スイス、38歳)は2023年、世界の6つの都市(東京、ボストン、ロンドン、ベルリン、シカゴ、ニューヨーク)で開催されるマラソン6大会「ワールドマラソンメジャーズ」のすべてで優勝し、完全制覇した。
レースで勝つだけでなく、記録についても世界トップだ。2021年11月の大分国際車いすマラソンで、1999年以来更新されていなかった世界記録を22年ぶりに塗り替えた。彼が出した世界記録は1時間17分47。2024年3月現在、この記録に迫り、さらに塗り替える可能性を感じさせる選手は出てきていない。
世界パラ陸上競技連盟(WPA)公認のマラソンで出された記録を基に作られる世界ランキングをみると、2023年のシーズンの1位はマルセル・フグで、記録は1時間17分06だった。彼に続くランキング2位と3位の記録は同タイムで1時間23分49、4位1時間23分58、5位1時間25分10。
42.195キロのマラソンの好タイムを比べても、1位のマルセルと、2位以下の選手との間にはっきりとした差がある。世界記録をさらに更新する可能性が高いのは、他の選手ではなく、マルセル自身かもしれない。彼は、車いすマラソンの「絶対王者」と言って過言ではない選手だ。
3月初旬に開催される東京マラソンは、ワールドマラソンメジャーズの6つのレースのうち、1年の最初のレースとなっている。
この2年(2022年、2023年)の東京マラソンは、マルセル・フグが独走となり、2位以下の選手を大きく引き離してゴールテープを切っている。一気に加速できる瞬発力、圧倒的なトップスピード、高速のまま走り続ける持久力。他の選手たちと比べて段違いの力を持っている。彼は1年のシーズン初めに、この東京で「絶対王者」の強さに陰りがないことを印象づけていた。
しかし、今年の東京には、彼がいない。
東京マラソンのレースディレクターを務めている副島正純氏は、車いす招待選手の報道発表資料の中で、「ここ最近、多くの大会でフグが主導権を獲り、優勝することが多かったのですが、フグ不在の東京マラソン2024は一体、誰がレースを作り、誰が最初にフィニッシュラインを駆け抜けるのか、レースの予想が難しい反面、面白いレースになるだろうと期待しています」とコメントを寄せていた。
絶対王者不在の東京マラソン。
他の選手たちに、優勝のチャンスがまわってきた。そのチャンスを掴もうと、複数の選手が接戦を繰り広げるかもしれない。今回出場する有力選手の中で、誰が、どの地点で、集団から先頭に飛び出すのか。東京駅の赤レンガの建物を背景に、ゴールテープを切るのは、誰なのか。東京マラソン車いすのレースを取材する予定の記者たちは今回、改めてマルセル以外の出場選手に注目し、最近の成績などの情報を確認しているかもしれない。

3月3日。東京の上空は青く澄み渡っている。
東京駅の丸ノ内改札口を出ると、すでに、東京マラソンのゴールが設置されていた。これから始まる交通規制のため、警察官の姿があちこちに見える。丸ノ内のオフィスビルにある取材者用のプレスセンターまで歩いて向かう。頬に当たる外気は、寒くはなかった。スマホで確認した気温は9度。マラソンを走るランナーには少し暖かいかもしれないが、暑すぎることはないだろう。
オフィスビルの7階に設けられたプレスセンターの会議室には、大型のスクリーンにテレビ画面が映し出されていた。東京都庁前のスタート地点には、競技用車いす(レーサー)に乗った選手たちが列をつくって並んでいる。一番前列に並んでいるのは、国際大会などで実績のある有力選手たちだ。
彼らの様子を伝えているアナウンサーの髪の毛に動きがあるかどうか、目を凝らす。スタート地点付近には、風がほとんどないようだ。気象条件は、絶好のマラソン日和になっている。
午前9時5分、号砲が鳴った。
選手たちの両手が、レーサーの車輪の外側に付いている漕ぎ手(ハンドリム)をぐっと下へ押しだした。選手たちの背中で肩甲骨がいったん寄り、左右に広がる。上腕の筋肉がぎゅっと収縮し、ぐんと伸びる。両腕から両手へ、さらにその先のレーサーのハンドリムへ伝えられた力が、レーサーを前へ動かしていく。レーサーの車体が滑るように走りだし、徐々にスピードが上がっていった。

「チャレンジしたい。1時間21分台を目標にしたいです」
レースの2日前に行われた招待選手の記者会見で、昨年の東京マラソン2位の鈴木朋樹(トヨタ自動車、29歳)は、42.195キロの目標タイムを口にした。具体的な記録を目標に掲げたのは、今夏にフランス・パリで開催されているパラリンピックのマラソンへの出場を目指しているからだ。
パリパラリンピック・車いすマラソンの日本代表選手は、日本パラ陸上競技連盟が定めた規定に基づき選考され、今年6月下旬に推薦される予定になっている。パリ・パラリンピック出場の可能性を高める方法の一つは、世界パラ陸上競技連盟(WPA)公認のマラソンレースで好記録を出し、記録に基づいて作られるランキングの順位をより上位へ上げておくことだ。このランキングで、鈴木は4位。今回の東京マラソンで、ランキング2位の選手の記録1時間23分49よりも好タイムを出せば、ランキングの順位を2位まで押し上げることができる。
1時間21分台は、2020年3月の東京マラソンで鈴木が出した大会新記録1時間21分52を踏まえたものだ。
「2020年の大会で、そのくらいのタイムで走っているので、できないことはないと思っています」
目標は、明確だ。それを口にできるのは、達成できるという自信があるからではないか。東京マラソンに向けたトレーニングで、自身の走りに良い手ごたえを感じているのかもしれない。
東京都庁前のスタート地点から神田方面へ長く続く坂道を、選手たちが一気に下っていく。序盤5キロから10キロまでの間に、7人ほどで形成されていた先頭集団から2人、3人と選手が振り落とされていく。選手同士は時々、急激にスピードを上げるなどの「揺さぶり」を掛けあっているようだ。
ある選手が急に加速すると、他の選手たちも離されまいと対応して速度を上げる。速度を上げるタイミングが遅れると選手間の差が開き、加速した選手が一気に前へ出て、遅れた選手は引き離されてしまう。急激に速度を上げるとその分、体力を使う。前の選手と間にできた差を詰めるのにも体力が要る。揺さぶりの主導権を握ることができるのは、急激な加速ができる能力を備えた選手だ。揺さぶりを繰り返しかけても余裕のある体力、持久力を備えていることも必要になる。
コースは坂道から比較的平らな道路へ出て、神田から浅草方面に向かう。10キロ付近、優勝候補は鈴木朋樹とダニエル・ロマンチュク(米国、26歳)に絞られた。ダニエルは、ワールドマラソンメジャーズで、マルセルに次いで2位に入る実力を持っている。彼が両腕を拡げると2メートル近くになり、長い腕を活かしてダイナミックにレーサーを漕ぐ。
一方、鈴木はダニエルと比べると小柄な体格だが、一定のリズムを刻むような漕ぎでレーサーを推進させていく。腕を振り上げて、ハンドリムをキャッチし、押し出す。その1回1回の動作に、力のロスを感じさせない。両腕の流れるような動作の繰り返しが、レーサーの車輪の回転数を上昇させていく。
鈴木はダニエルに対して、どの地点で、どう仕掛けるのか。それとも、ダニエルのほうが先手を打って飛び出し、鈴木を後方に引き離すのか。
勝負は、18キロの浅草付近で決まった。
鈴木が1人単独へ先頭に出た。ダニエルとの差がみるみると開く。ダニエルの走りに、その差を詰めていく気配はなかった。ダニエルの姿が後方に小さくなっていき、テレビカメラで捉えきれなくなった。

ゴールテープを切った鈴木の記録は、1時間23分05。目標としていた1時間21分台には届かなかったが、ランキングの順位を上げることは成功した。
優勝した鈴木は、レースを振り返り、「ダニエル選手と前半に仕掛け合いがあり、めちゃくちゃきつかったです。浅草付近から一人で走る展開となり、そこからは自分との闘いでした」と話した。
目標に掲げていた1時間21分台は達成できなかったが、今回の記録はランキング2位に入る記録になったため、その点は評価していいポイントだと位置付けた。
マルセル・フグが不在だったことの影響について問われると、「正直なところ、誰かと一緒に走ったほうが、より確実にタイムを達成できたと思います。一人で走ることになると自分との闘いになりますし、メンタル的にキツイ状態ではありました」と鈴木。マルセルが不在のレースで、自分自身との闘いになることを想定して、トレーニングを積んできたと話した。
レーサーは複数の選手で走る時、1列に並んで互いに先頭を交代して走るローテーションをすることができる。ローテーションは、前を走る選手を風避けにして体力を温存することができ、高速のスピードを維持して走り続けることを可能にする。ただし、実力に差があるとローテーションをすることは難しい。ローテーションが成り立たなくても、力のある選手のすぐ後ろに付き、できるかぎり長い距離をその背中を追いかけて走れば、好記録に繋がる可能性は高くなりそうだ。
マルセル・フグが出場していたら、優勝争いはどうなっていただろう。彼と一緒にローテーションして走っていたら、さらに好記録を狙えただろうか。
絶対王者は、むしろ不在であることで、その存在の大きさを改めて感じさせるのかもしれない。
(取材・執筆:河原レイカ)
(写真提供:小川和行)