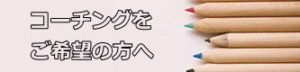JR高崎駅ビル内のスターバックスは、大学生のカップルや女子高生たちで賑わい、隣の席から甲高い笑い声が響いてくる。
私が仕事の帰りに立ち寄る東京・神保町のスタバでは、ノートパソコンを開いて書類を作成している人や、商談か打ち合わせをしている人の姿が珍しくないが、この店舗では一人で仕事をするビジネスマンは浮いてしまいそうだ。
同じスタバでも、どの地域にあるかによって、集まる人がまったく違う。
都内で生活している私と、群馬県前橋市で暮らしている関口紘樹さんとは、日々の生活の中で見ている風景が違うのかもしれない。
公紀の練習をみている関口さんは、特別支援学校の教員として働いている。
2017年4月から正式採用され、臨時教員だった期間を入れても教員歴はまだ1年半。
隣の席で談笑している大学生たちに混じっても違和感がないだろう。
「これまでも国内の陸上大会で公紀に同行したことはあったんですけど、今回のパラジュニア世界選手権は計11日間、公紀と一緒に寝て、起きて、すべての食事も一緒です。まず、そのことに大丈夫かなという不安がありました。競技のことよりも、生活面での不安が大きかったです」
関口さんが公紀と出会ったのは、大学4年生の時。
都内の大学で学んでいたが、卒業後の進路として教員を志望していた。
教育実習で母校に挨拶にいった時、家庭科の教師・反町由美さんに再会した。
公紀の母・由美さんは、関口さんが高校3年生の時、大学への志望書を添削したり、面接を指導した。
由美さんの記憶の中にいる高校生の関口さんは、同級生たちがAKB48に夢中になっている時、レディ・ガガを聴いているような大人びた男子生徒。当時の陸上部は力のある選手が揃っていたが、その中でも中心的な選手だった。
「障害のある子どもたちが可愛いんです」
関口さんは、もともと保健体育の教師になりたいと思っていたが、大学でボランティアなどをするうち、特別支援学校に興味を持った。
障害のある子どもたちとの関わりを楽しそうに話す関口さんを見て、由美さんは息子・公紀の話をした。
障害者スポーツにも関心があると知り、教師から母親の顔になった。
「よかったら、公紀の練習をみてもらえない?」
「群馬に帰省した際でよければ、練習をみますよ」
それがきっかけとなり、練習をみる関係が今まで続いている。
休日には、公紀と高崎市内の運動場などで待ち合わせ、一緒に走る。
軽いジョグをした後、足上げ、腕を振りなど走りの基本的な動きを繰り返す。
トラックを何本か流して走った後は、スタートダッシュをする。
中学生の部活動で毎日実施されているような基礎的な陸上の練習を淡々とこなしていく。
「公紀の良いところは、走ることが好きなところです」
関口さんが動きを示すと、公紀はそれを習得しようと真似をする。
目で見たとおりの動きを真似て、すぐにできるわけではない。
足の運び方を間違えたり、左右の動きがずれたりする。
何度も繰り返して、少しずつ目標の動きに近づき、数カ月から半年でようやくできるようになる。
一つの動きを覚えるのに、1年近くかかったものが、今年に入ってからは覚えるまでの時間が3カ月程度になり、徐々に短くなってきた。
「とにかく、速くなりたいという気持ちが強いです」
公紀が走る姿を見るたび、関口さんは、そう感じている。
パラジュニア世界陸上の大会期間中、公紀を一番近くで見ていた関口さんに、私はどうしても聞きたいことがあった。
公紀が出場する100mを観に行くべきかどうか、母親の由美さんが悩むことになったのは、なぜか。
関口さんは、その理由を知っているはずだ。
それは時間が経てば誰の記憶にも残らないほど、ささやかなことなのかもしれない。
母と息子あるいはコーチと選手の関係の中でよくある些細な諍いで、喧嘩とも呼べない小さな衝突だったかもしれない。
そうであったとしても、私はそれが何だったのか知りたかった。
紺色のポロシャツにコットンのパンツを身に着けている関口さんは、ついさっきまで自宅でのんびりと過ごしていて、ふらっと近所に出てきたような雰囲気だ。
向かい合って座っている私は、一番聞きたい質問を胸に隠したまま、背中が緊張している。
私の質問は、公紀と関口さん、そして由美さんの人間関係に触れるものだからだ。
関口さんは、由美さんに遠慮して、あるいは公紀を気遣って、公紀の良い面しか話してくれないかもしれない。
人間関係を拗らせたいわけではないが、公紀の良い面も悪い面も、関口さんの本心を語ってほしかった。
茶褐色のテーブルに置かれた白地のマグカップを持ち上げると、スタバののロゴマークの顔が笑っていた。
「公紀君に、パラジュニアの反省をLINEで尋ねてみたら、イライラして、関口コーチとケンカしたと伝えてきたんです」
口火を切ると、私の背中に一筋、汗が流れた。
関口さんの長い睫が、かすかに揺れた。
瞳はほんの一瞬、宙を見上げ、再び元の位置に戻った。
マグカップについている緑色の笑顔は、関口さんのほうを向いている。
「公紀の様子を見ていて、何か探しているな、何か言いたそうだなという雰囲気を感じる時がありました。でも、僕は、あえて気がついていないふりをしました。公紀がホワイトボードに何か書いて伝えてきたら、それを聞いて、対応するようにしたんです」
公紀から言葉で伝えてもらわなければ、分からない。
それは、彼を取材している私も同じだ。
スイスに出発する約1カ月前、町田市で開催された関東パラ陸上競技大会で、公紀にパラジュニア世界陸上への抱負を尋ねた。
公紀は、頭を少し傾けて考えていた。
その姿は、脳の底から一文字一文字をひねりだし、自分の考えていることと、それを表す文字が合っているかどうかを確認しているように見えた。
黒いマジックペンのインクがホワイトボードの上に乗り、「大会で、自分が頑張ります」という意思を示した時、私には安堵に近い感情が沸いた。たった一言でも、公紀を知る手がかりがそこにあったからだ。
パラジュニア世界陸上で、関口さんは公紀をサポートする役割を引き受けたものの、生活面では何をどこまで手伝えばいいのか分からないまま、ぶっつけ本場で臨んでいた。
公紀は、嚥下に障害があるため、料理を細かく刻んだ状態で口に入れる必要がある。
関口さんは、由美さんから預かった調理用の鋏で料理を細かくし、公紀の食事を手伝った。
ホテルには洗濯機がなく汚れた衣類は手洗いするしかなかったが、公紀は右手が硬縮しているため、水を含んだ衣類を絞ることが難しい。関口さんは公紀の洗濯を引き受けた。
ホテルにチェックインすると間もなく、関口さんは、公紀が自分のほうをじっと見つめていることに気がついた。
時々、ニヤッと笑ったりもする。何か話しかけてもらいたいという雰囲気を漂わせる。
それにどう反応してよいか考えた末、公紀が醸し出す雰囲気を察することは辞めた。
話す必要がある場合は、公紀自身が言葉にして伝えることが必要だと思い、気がつかないふりをした。
公紀は、苛立ちを滲ませた。不穏な空気が徐々にホテルの一室に充満した。
自宅で過ごしている時のように食事や睡眠が十分に満たされていれば、多少のストレスがあっても気にならない程度で済んだかもしれない。
しかし、スイスでのホテル暮らしはそうはいかなかった。
思い通りにならないことを、「まぁ、いいか」「仕方ない」とやり過ごすことができず、公紀の苛立ちが積もっていった。
「最初の種目の200mは、計測機器の不具合で、競技の開始が1時間ほど遅れたんです。スタートの音も、パーンと甲高い音なら反応して飛び出しやすいのですが、音が小さくて聞き取りづらかった。公紀だけでなく、他の選手もスタートの反応が難しかったと思います。公紀は、200mを走り終わった後、やっちまった、という顔をしていました。自分の走りが良くなかったことは分かっていたと思います。ゴールをした後、苛立ちが表に出てきました」
関口さんは、競技を終えた公紀に「クールダウンをしておいでよ」と声を掛けた。
公紀はそれを聞かず、無視した。
日本代表の選手やスタッフが集まっている群れとは別の方向へ歩き出し、一人で離れていった。
「一人にしてくれ。クールダウンなんて、そんなことをやっている場合じゃないんだ」
関口さんには、公紀の態度がそう言っているように見えた。
交通事故で公紀が救急搬送された病院では、命を救ってくれた医師や看護師たちが応援してくれていた。
大学に進学した中学校の同級生たちには、自分は陸上で頑張っていることを伝えたかった。
目標は自己ベスト更新。良い結果を残したい。
日本を出発する前から、公紀の心の中には、熱く燃えているものがあった。
しかし、最初の種目200mを失敗した。
スタバのマグカップに付いている笑顔は、多くの人が親しみを感じるようにデザインされたロゴマークだ。
記憶に刷り込まれ、その顔を見るだけでコーヒーの香ばしい香やほろ苦い味を思い出す人もいる。
言葉にしなくても、伝わるものがある。
「結構な態度でしたよ」
関口さんは、プラスティックの透明なカップを手に取り、ストローを口にした。
カップの表面には細かい水滴が付いている。
氷はすっかり溶けて、もう形を残していない。
スイス滞在中の公紀の態度や様子は、関口さんから由美さんへのLINEで細かく伝えられていた。
競技場の観客席から公紀の態度を目にした由美さんは、次に予定していた100mを観戦するかどうか悩んだ。
母親が見守っていることが、公紀の「結構な態度」を増長させる要因になっているかもしれないと感じたのだろう。
「ホテルの部屋で、公紀が何かしてほしそうな雰囲気を出していても、僕があえて気がつかないふりをしたのは、自分から伝えないとダメだということを理解してほしかったからです。ただ、パラジュニアの世界選手権という場で、僕がそういう対応をするべきことなのかどうかという思いはありました」
自分の選択が正しいのかどうか、関口さんにも迷いはあった。
私が、関口さんの立場だったら、どのように対応しただろうか。
公紀が居心地よく過ごせるように気を遣い、「何か、困っていることはない?」と四六時中、声を掛け続ける気がする。
料理は切り刻み、公紀が飲み込めるかどうか一口ずつ確かめるように見守るだろう。
公紀の鞄の中から洗濯物を取り出し、公紀から要望されるよりも先に、洗って干してしまうかもしれない。
公紀のことをよく知らないぶん、彼に対して何をしたらよいか不安になり、何かすることで不安を打ち消そうとしたに違いない。
しかし、手を貸して助けることが良いことなのかどうかは、時と場合に依る。
他人の手助けを得られないことで、自ら考え、行動する覚悟が決まるかもしれない。
行動した結果が失敗しても、それは経験となり、次の挑戦につながることもある。
逆に、手助けを得られないことで、最初の一歩を踏み出すまで時間が掛かり、挑戦に適したタイミングを逃すかもしれない。
失敗が心の傷となり、不安を増幅してしまうこともある。
困っている人に手を貸すことは、その人が壁を乗り越えるのを助ける。
手を貸した相手から感謝されれば、悪い気はしない。
困っている様子を見ながら何もしない時に沸いてくる罪悪感とは無縁でいられる。
公紀の様子を見て、何に困っているかを察してくれる人ばかりではない。
公紀の障害や日常生活をよく知らない相手には、自分から何をどうしてほしいのかを言葉にして伝えなければ、理解してもらえない。
自分の思いを自分で伝えることがなければ、新しい人間関係も始まらない。
関口さんは、パラジュニア世界陸上の結果だけでなく、これから先の公紀のことを想っていた。
そして、あえて気が付かないふりをするという自分の態度を決めたのだ。
スタバを後にした私は、高崎駅から新幹線に乗車し、座席の前についている机を下ろした。
ノートパソコンを開くには窮屈だが、関口さんから聞いたことを少しでも早く記録しておきたかった。
キーボードで文字を打ち込み、エンターキーを押すと、候補の漢字がずらりと出てきた。
漢字を忘れていても、ある程度は、パソコンのソフトが候補を上げてくれる。
公紀の脳は、パソコンのソフトのようにはいかない。
自分が言いたいことを表す言葉を脳の奥から取り出し、ようやく一言を発している。
私はスマホを取りだし、LINEで公紀とのやりとりを見返した。
「結果はどうでしたか?」
「自分は負けたよ」
「今日は、どんな練習をしますか?」
「午後からは、3時でトレーニングします」
「練習内容を教えてください」
「坂練習を書きました」
「シャトルラン72回でベスト」
「関東選手権の目標は?」
「負けないとして練習です」
「大会でチャレンジ心してメダル狙います」
公紀の返信は、短い文でつづられている。
その一言、一言の間に、公紀の気持ちや考えが埋もれている。
私はそれを手探りで掘り出し、拾い上げようとしている。
スイスのホテルで関口さんがとった対応は、公紀には、頑なに見えたかもしれない。
関口さんの揺るがない態度に、公紀は自分の不満や苛立ち、怒りをどうしようもなく、そのままさらけ出すしかなかったのだろう。
私は、ずっと待っていた。公紀の心が揺れ動く瞬間を。
LINEで記される言葉と言葉の間にあるものが、より鮮やかに見える瞬間を待っていた。
スイスの競技場での出来事は、まさにその瞬間だ。
そこには公紀をより深く知る手がかりが、たくさん潜んでいる気がした。
【取材・執筆】河原レイカ
【トップ掲載写真提供】反町由美さん
- 投稿タグ
- 企画特集