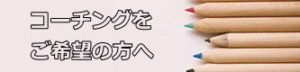東京・町田市営陸上競技場の観客席の裏手は、鼠色のコンクリートで囲まれた幅広い廊下が続いている。
その壁に添って赤や青のレジャー用ビニールシートが並べられ、ゼッケンを胸に付けた陸上選手たちが、
午後の競技が始まる前の時間を潰していた。
2017年7月1日、パラ陸上関東選手権大会第1日目。
ランニングシャツを着た細身の男性選手は股関節をゆっくりと拡げている。
足の筋をほぐしながら、瞳を閉じて何かを念じるようにしている。
頭の中では次の種目の目標タイムを計算しているのかもしれない。
投擲の選手が、バスタオルを被って横になっている。
白い布地の端から、上腕の太い筋肉が覗いている。
その筋肉をギュッと縮めて蓄えたエネルギーは、砲丸が手から離れる瞬間、一気に放出されていた。
午前の競技中、曇り空の下で、弧を描いて飛んでいった砲丸がやけに軽そうに見えたことを思い出した。
廊下ですれ違う選手たちと挨拶を交わしながら、スマホでLINEのアプリを開くと、
昨日の夕方、届いたメッセージが一番上に残っていた。
8月3日から6日まで、スイスのノットビルで開催される「世界パラ陸上競技ジュニア選手権大会」
(パラジュニア世界陸上)の派遣選手が発表されたことを知らせるものだった。
日本代表に選ばれた選手に、一言、お祝いを伝えようと探していた。
その選手は、廊下の先のほうで、片膝を立て、背中を少し丸めて座っている。
まるで遠足にやってきた小学生のようだ。持参したお菓子でもつまんでいるのか、
携帯でゲームを始めているのか、のんびりした雰囲気が漂っている。
近づいていくと、短髪の頭に一筋の白い手術跡が残っているのが目に入った。
反町公紀(そりまち・まさとし)だ。
「こんにちは」
公紀はゆっくりと私を見て、頭を少し傾けて会釈する。
私の顔は、覚えているようだ。
ビニールシートの上に置かれていたA4サイズのホワイトボードを手に取り、黒いマジックで文字を書く。
「日本代表、おめでとう」
公紀に見せたが、表情は変わらない。
文字をぼんやり眺めながら、まるで自分の事ではないかのように不思議そうな顔をしている。
母親の由美さんから届いたLINEには、「バンザイしてましたよ」と書かれていた。
初めての日本代表だ。嬉しくないはずがない。
家族の前では、素直に喜びを出せるのだろうか。
それとも、公紀の喜びは、1日経つとどこかに飛んでいってしまうものなのか。
私はもう一度、ホワイトボードを手に取った。
「日ノ丸、身につけます。コメントをお願いします」
公紀が、首を傾げている。
私の伝え方が下手なのだろうか。
パラジュニア世界陸上に向けた抱負を求めて「コメント」と書いたのだが、伝わらないのか。
公紀が何を考えているのか、分からない。
もしかしたら、何も考えていないのかもしれない。
黒髪の奥に残る一筋の白い跡が、くっきりと浮き上がって見えた。
トレーニングをサポートしている関口紘樹さんが、公紀の顔を覗き込んで、微笑んでいる。
学校教員の関口さんは、休日に公紀と一緒に走っている。
関口さんには、公紀が言いたいことが想像つくのかもしれない。
「ほら、反応して」
関口さんが促すと、公紀の瞳が動いた。
「ふぅ~」
言葉にならない声が漏れた。
その声は、「今から、書くとこなんだよ」とか、「急かさないでよ」か、そんな感じの何かだった。
公紀が黒いマジックのキャップを外し、ホワイトボードの上をのろのろと走らせ始めた。
「大会で、自分が頑張ります」
公紀の瞳が、私を見た。
黒い瞳が、「どうですか?」と言っている気がした。
私は、一つ頷いて、返した。
「いいですね」
カメラを手にして立ち上がり、手のひらを下から上へ動かして、公紀にホワイトボードを持って立つように促す。
公紀が、タオルで口元の涎を拭い、立ち上がった。
レンズの焦点を公紀の顔にあわせながら、自分の口角を上げて指で差し、声を掛ける。
「笑顔で!」
公紀が、はにかんだ。
「ふぅ~」
言葉にならない声が漏れた。
彼の心の中が、ほんの少し見えた気がした。
【つづく】
(取材・撮影:河原レイカ)
- 投稿タグ
- 企画特集