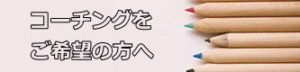【7】
陸上選手が目指す最高峰の大会がオリンピックなら、車いす陸上選手が目指す最高峰はパラリンピックだ。パラリンピックは4年に1度、オリンピックと同じ年、同じ国で開催されている。
日本代表選手に選ばれるには、国際パラリンピック委員会(IPC)のランキング上位に入るなどの条件を満たすことが必要になるが、まずは、国内の大会で上位に食い込んでおかなくてはならない。
学生時代から常に高い目標を掲げる小島が、パラリンピックを目標にするのは当然のことだった。
「自分の走りをつかんだ気がしたのは、2014年のシーズンが終わる頃ですね。まだまだですけど、手ごたえみたいなものを少し感じるようになっていました」
2014年は、ロンドンパラリンピックから2年経ち、次のリオパラリンピックまで残り2年という中間年にあたっていた。パラリンピック出場を目指す選手たちは、あと2年あるなどと悠長に構えてはいられない。2015年に入れば、日本代表を選考するレースが始まる。
2014年は、「次の日本代表は、自分だ」といわんばかりの走りで、ライバルたちを凌いでおきたい時期だった。
大阪・長居陸上競技場、障害者陸上の日本選手権。午前の競技が始まるまで30分ほど時間があった。
太陽が擦れた赤褐色のトラックをじりじりと焼いている。
地面から上がった水蒸気をたっぷり含んでいるせいか空気が重く、蒸し暑い。
呼吸するたび、吸い込んだ息が体の中で鉛のように蓄積し、徐々に重くなっていく。
ビジネスホテルのベッドを出てからずいぶん経つのに、頭の中がどんよりしている。
競技が始まるまでに、気分だけでも軽くしたい。
私は、デジタル一眼レフカメラを首から下げたまま、トラックの外側をゆっくり歩き始めた。
視覚障害の選手が体を慣らすようにゆっくり走っている。
隣を走る伴走者が声をかけるたび、選手の口元が微笑んでいる。
義足の女子選手たちが競技場の隅のほうで腰をおろしている。
彼女たちの輪からは、通学途中の女子高生のような甲高い笑い声が弾けていた。
レーサーのタイヤがシューッと音を立てて近づいてくる。
内側のレーンを走ってきた車いすの選手が、足取りの重い私を追い越していった。
通りすぎた選手の背中は、他の選手と比べて一回り小さい。
腕も細く、華奢な印象だ。
しかし、車輪を漕いでいる上腕の力は、体つきからイメージするものより、ずっと強かった。
小島将平は、まっすぐ前を見ている。
その目がとらえているのは、競技場のトラックではないようだ。
何かを考えながら走っているのか。それとも、頭の中を空っぽにして走っているのか。どちらでもない気がする。
ウォーミングアップの時から一心不乱に、全力で走る選手は他にいない。
本番まで時間があるにもかかわらず、小島は、これからすぐにスタートラインに並ぶのではないかと思わせた。
車いすの選手は大勢いるが、小島は他の選手と何かが違う。
小柄な体なのに、トラックのどこを走っていても、すぐに小島だと分かった。
本格的な練習を始めてわずか2カ月で、フルマラソンを完走したことのある選手だ。
予想を裏切る走りをするのかもしれない。
【8】
太陽が、一番高いところに上がった。
ヘルメットの内側に湿気が籠り、染み出した汗は髪の毛を辿りながら露になり、地面に落ちた。
男子1500m、予選1組。
出場選手は8名。上位3着までに入れば、決勝進出が確定する。
9レーンに入った小島は、レーサーを静止させると背筋をすっと伸ばした。
漕ぎ手に添えていた両手をそっと離し、重力に任せるようにふわりと下ろす。
肩から上腕へ、肘から手首へ、そして手の指先まで。
骨と筋肉の連なり一つ一つから、余計な力みを取り除く。
「僕は、走りが硬いといわれていたんです。
学生時代にコーチからそう言われていましたし、ビデオで撮影した映像を見て、自分でも走りが硬いと思いました。
無意識に力が入ってしまい、肩が少し上がるんです。
走りが硬くなると、その分、自分が持っている力を余計に使ってしまいます。
力をロスするんです。本当に使いたい時に力が残っていないと、粘りのある走りはできません。
だから、スタート前には、特に意識して、リラックスするように心掛けているんです」
ハンドリムにそっと手を添えて、体を前傾させる。体の動きを止めると、一瞬の静寂が小島を包んだ
号砲が鳴った。
上腕の筋肉が大きい選手が一人、勢いよく前に出た。
飛び出した選手を逃がすまいと、他の選手たちが次から次へと追いかける。
縦一列になったレーサーがトラックのコーナーを曲がり、ホームストレートに入ってきた。
レーサーで走る選手を正面から見ると、体を前傾させて再び起こす動作が、お辞儀のように見える。
上体のすべてを使った力強いお辞儀が一列に並んで近づいてくる。
私はゴールラインの先に設けられている撮影用のエリアに入り、カメラを構えた。
小島は、8名の選手の後方、7番手につけている。
ファインダーの奥に小さく見えていた頭が深く下がり、再び、上がるのを繰り返し、少しずつ大きくなってくる。
体が起き上がった瞬間、小島の顔が見えた。
小島は、まっすぐ前を見ているが、今、ここにある景色を見ているように思えない。
2周目に入ると、選手は2つの集団に分かれ、決勝進出の3枠は上位4名の争いに絞られた。
小島は後ろの集団に入り、7番手のままだ。前の選手との間が少し空いたが、焦っている様子には見えない。
一定のリズムでハンドリムを押して、淡々と走っている。
観客席から小島の名前を呼んでも、小島の耳には入らないだろう。
走っている時の小島は、自分に必要ない音をすべて遮断しているように見えた。
最後の1周を示す鐘が鳴った。
上位4名の選手たちのスピードが一段、上がった。
どこでラストスパートに入るか、互いに様子を見ているようだ。
荒くなった息づかいが聞こえてきた。
小島は、両腕を勢いよく、後ろに引き上げた。
背中で肩甲骨が動いている。両肘を伸ばしながら降ろし、黒いグローブをはめた手をハンドリムに添えた。
背中から肩へ、上腕から肘へ、さらにその先へ。
凝縮されていった力が、小島の手から車輪に伝えられていった。
スピードがぐんと上がった。
向かってくる風が強くなっているはずだが、小島はそれを頬で感じることを忘れているにちがいない。
レーサーのタイヤが音を立てながら近づいてきて、小島の横顔が私の前を通り過ぎた。
小島は、まっすぐに前を見ていた。
その目が何をとらえているのか、分からない。
その耳は音を受け取っていない気がする。
全力という言葉では収まらない。
体力の限界も、気力の限界も超えようとしている。
心の奥底から沸きだす何かが、小島を突き動かしているのではないか。
なぜ、君は、そんなふうに走るのか。
ビジネスホテルの部屋は、薄っぺらのカーペットから微かに煙草の香りがした。
テレビを壁のほうへ近づけると、細長い机のスペースがほんの少し広くなった。
パソコンを開いて、日本パラ陸上競技連盟のウェブサイトから過去の大会記録を探すと、1年前の日本選手権の記録が出てきた。
小島は、1500mを4分36秒24で走っていた。
炎天下で行われた今日の1500mで、小島は7着。
決勝進出は果たせなかったが、記録は3分43秒26。
2013年から2014年の1年間で、1500mの記録を52秒98縮めていた。
1500mの日本記録は2分59秒84。
3分を切るタイムは、パラリンピックでメダル争いをする選手たちに肩を並べる記録だ。
もちろん、それは、すぐに手が届く記録ではない。
山の頂に立つのは、簡単ではない。
しかし、小島は、この1年で記録を大幅に縮めている。
はるか遠くにあった山の頂が、ぐっと近くになっていた。
(取材・執筆/河原レイカ)
- 投稿タグ
- 企画特集