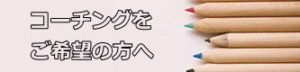【5】
花岡は、くせの強い髪を両手で前から後ろへかきあげた。
現役を引退してから体を動かす時間は大幅に減ったが、ポロシャツの半袖から出ている上腕の筋肉は、
小島のそれよりも一回り大きい。その腕を胸の前で組みながら、記憶を遡っている。
隣に座っている小島は、学生時代を上下関係の厳しい体育会系で過ごしたためか、いつも以上に姿勢
を正している。花岡の言葉を一つも聞き漏らさないように、じっと耳を傾けている。
都内に出てきた花岡を誘って、小島の家を訪ねた。
この数カ月、私は月に1回か2回の割合で、小島に話を聞きに来ている。だが、花岡を交えて話をすれば、
まだ知らない小島の一面が出てくる気がした。
午後17時を過ぎたが、リビングに陽が差し込んでいる。部屋の蛍光灯はつけないままで十分、明るい。
花岡は、額にうっすら汗を浮かべている。小島がエアコンのスイッチを入れると、さらりとした風が流れはじめた。
美幸さんがコーヒーを淹れてくれた。テーブルを囲んだ3人の顔の前で、香ばしい湯気が立ちのぼり、風に乗っていった。
「小島君には、まず、レーサーに乗って体の左右のバランスを保つことから始めてもらいました。
大阪マラソンの頃は、ようやくレーサーに座って姿勢を保てたところで、走りについてどうこうアドバイスする段階ではなかったんです」
花岡が、小島の練習を本格的に見るようになったのは、大阪マラソンの2カ月前からだった。
骨盤から下がない小島は、レーサーに座った時に体の左側が沈み、体の左右のバランスがとれなかった。
姿勢をまっすぐに保つため、左脚の位置に何かを詰める必要があった。どう走るかの前に、どう座るかが課題だった。
最初は大小のクッションを使って、左脚があるべき場所にできている隙間を埋めた。
しかし、クッションの組み合わせ方や置き方は毎回、同じにすることができない。
レーサーに乗るたびに、クッションの調整に時間がかかるようでは困る。
いつ、どこでレーサーに乗っても、左右のバランスをとれるようなものが必要になった。
義足をつくる義肢装具士に相談すると、小島の体にあわせて、スチール材で円筒をつくってくれた。
左の尻と太腿の代わりになる詰め物だ。それをレーサーの座席に置いて座ると、小島の姿勢はようやくまっすぐになった。
「小島君のように骨盤から下を切断してレーサーに乗っている選手は、国内では他にいないんです。
海外でも、いないんじゃないかな。同じ車いすでも僕とは障害の状態が違いますから、
僕の経験知からでは分からないことがある。だから、小島君には、分からないことは、
いろいろ試させてねと言っていました」
花岡が視線を送ると、小島が深く頷いた。
「左側の背筋が使えないことが分かったのも、僕が練習を見るようになって、
しばらく経ってからでした。レーサーを漕ぐたびに、小島君がしんどそうにしていて、
やれやれという感じだったんで、おかしいなとは思っていたんですけど。
最初は、まさか背筋が使えていないなんて、想像できていなかったんです」
レーサーに乗っている選手たちは、上半身を前傾して、車輪を漕ぎ、時折、上体を起こす。
体を前傾する動作と、体を起こす動作は、基本中の基本になるものだ。
小島の左側の背筋は、付け根となる骨を失っていた。体を前傾するのも、起こすのも、
右側の背筋が頼りだが、入院中に落ちてしまった筋力はまだ十分に取り戻せていなかった。
体力も筋力も整っていたわけではない。それでも、小島は走ろうとした。
「そんな体の状態で走るなんて、最初の頃は、大変だったんじゃないですか?」
口にした瞬間、私は、あまりにも稚拙な質問だと気がついた。
「大変だった」以外の答えは、ありえない。恥ずかしくなり、質問を重ねた。
「レーサーを漕ぐのに、こんなところに苦労したとか。特に練習をしなければ
いけなかったところとか、ありますか?」
小島は、う~んと首を傾げて考えている。
「レーサーに乗り始めた頃は、とにかく必死でした。最初はどんな感じで漕いでいたのか、
何をどう練習していたのか…。改めて思い返してみるんですけど、よく覚えていないんです。
とにかく、必死で。必死だったという感じだけです」
宙を眺めていた花岡は、記憶の線上に何かを見つけた。
「そういえば、練習で5000mのタイムを計った時に、小島君が“大学生の時の自己ベストより遅いんです”
と言っていたことがありました。自分のタイムに腹をたてて、そう言ってきたんです」
100mを何秒で走れるか、フルマラソンの42.195kmを何時間何分何秒で走りきれるか。
自己ベストタイムは、自分の実力を示す指標の一つだ。
小島が学生時代に出した自己ベストは、大学生では国内トップクラスのものだろう。
しかし、車いす陸上では、小島はまだ競技を始めたばかりの初心者だ。レーサーに乗り始めたばかりの選手が、それほど速く走れるわけがない。
車いすの国内トップレベルの選手は皆、少なくとも数年の経験を積んでいる。
10年以上の経験を積んでいる選手も少なくない。
足で走っていた時のタイムと、レーサーで走ったタイムを比べる意味が、私には分からない。
小島が腹をたてたのは、なぜか…。疑問をノートに書き留めようとして、私は気がついた。
小島が腹をたてたのは、自分のタイムに納得していなかったからだ。
脚で走ったか、レーサーで走ったかは、関係ない。小島にとっては、どちらも自分の走りだ。
小島は学生時代の自己ベストタイムを超えるという目標をたてていたのだろう。
目標を達成できなかったから、自分に腹をたてたのだ。
私のペン先がノートの紙面から離れたのを見計らい、花岡が続けた。
「小島君は、最初から目標を高いところに掲げていましたね。
まだ筋力がついていないから無理だと言っても、国内上位の選手がやっている動きを真似して
やってみようとしていましたし。大阪マラソンも、小島君は完走を目標にしていました。
でも、練習を始めてから間もないころですし、筋力も持久力もそんなにない時でしたから、
正直なところ、僕は、小島君が完走するのは無理だろうな、と思っていたんです」
誰もが、小島がフルマラソンを完走するのは無理だと予想していた。
小島の両親も、妻の美幸さんでさえ、制限時間内に関門を通過するのは難しいと思っていた。
小島が途中リタイアとなって帰ってきた時に、どんな励ましの言葉をかけたらいいかを考えていた。
そんな予想を、小島は、見事に裏切ってみせた。
【6】
2012年11月、大阪マラソン。
初出場の小島は、車いすの選手の列の一番後ろにいた。
大阪城址公園前の沿道には、スタートする選手たちに声をかけようと大勢の人が集まっている。
車いすの選手たちの最前列で、招待選手が紹介されている。ロンドンパラリンピックに出場した花岡は、
この大阪マラソンを現役引退レースと位置づけていた。小島は、花岡を紹介するアナウンスが始まると、
姿勢を正して、耳を傾けた。
大阪マラソンのコースは、国立文楽劇場を通り過ぎ、銀杏並木で知られる御堂筋のオフィス街を走り抜ける。
観光名所の一つとなっている通天閣の展望台を見上げながら進み、大阪港湾方面へ入っていく。
風が、小島の顔をなでるように流れていった。
御堂筋も通天閣も通り過ぎたはずだが、よく覚えていない。他の選手とはずいぶん離されてしまった。
車いすの選手の最後尾。小島の後ろからは、自転車に乗った係員が付いてきていた。
関門とされている地点を制限時間内に通過しなければ、係員は走るのを止めるように声を掛けるつもりだろう。
「なんとか、制限時間に間にあってくれ」
小島は、息を一つ、大きく吸った。
難関は35キロ過ぎに迎える南港大橋だ。高低差が20m近くあり、上り下りの勾配がきつい。
最高時速35km前後で走る国内トップ選手も、橋の上りは時速10km以下にスピードが落ちる。
小島は、上半身で踏ん張るようにして、坂道を登っていった。
体を前傾させ、ハンドリムを一番下まで押すと、顔が地面にぐっと近づいた。
スピードはみるみる落ち、レーサーに付けている速度計の数字が二桁から一桁に減った。
歯を食いしばって漕いでも、地面からの抵抗を受けとめるのが精いっぱいだ。
目の前に高い壁が現れたような気がした。漕いでも漕いでも、思うように前へ進まず、
坂道から転がり落ちないように踏ん張っているだけになった。
ついに、速度計のデジタル表示が「0(ゼロ)」になった。
坂の傾斜でレーサーの前輪が地面から浮き、止まったことを示す数字だ。
「ここで、止まっている場合じゃないんだ」
小島は、腹筋に力を入れ、上半身の力を体の中心に集めた。
両腕を後ろに大きく引きあげ、上から下へハンドリムを押す。
加えた力が車輪をぐっぐっぐっと動かす。立ちはだかる壁に挑むように、小島は、
もう一度、両腕を大きく引き上げた。
ぐっ、ぐぐっ。
レーサーの速度計が、ゼロから1へ、3から5へ、再び、数を数えはじめた。
地面の抵抗に負けないように、小島は間髪を入れずに漕ぎ手を押した。
車輪がほんの少し軽くなり、進む距離が伸びた。
風の流れが変わった。
勾配が下りに入った。ハンドリムを押さなくても車輪が自ら転がり、
スピードがぐんぐん上がっていく。
前に立ちはだかるものは、もう何もなかった。
このまま、スピードに乗って、走り続けていけばいい。
小島は、大きく腕を後ろに引き上げ、ハンドリム を上から下へ押した。
押し出すリズムが、音楽のベースのようになって心地いい。
ターン、ターン、ターンと弾むようなリズムで押すと、レーサーのタイヤがそれに応えるように
シューッ、シューッ、シューッと音をたてて回った。
40kmを過ぎた。
「完走できる。ゴールができるんだ」
小島は、涙に濡れた頬をウェアの袖で拭った。
大阪マラソンのゴール地点で、小島は、どんな顔をしていたのだろうか。
ささやかな微笑みで、喜びを表したのだろうか。
フルマラソンを完走できたことに安堵していただろうか。
それとも、次の目標を思い、気を引き締めていただろうか。
「やっと、戻ってきたと思ったんです」
「…戻ってきた?」
「車いす陸上という、新たなスタートラインに立てた。陸上の世界に戻ってきた。
大学時代に一度は区切りをつけましたけど、ここから、また、陸上競技の世界で勝負ができると思ったんです」
(取材・撮影:河原レイカ)
⇒つづく
- 投稿タグ
- 企画特集