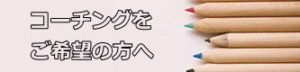【9】
「遅くなりましたが、あけましておめでとうございます。
新年早々、あまり良くないご報告で恐縮ですが、今月の上旬から再度、
築地のがんセンターに入院することになりました。
退院後、3年以上は何もなくこれたのですが、2014年末の検診で再発が発覚しました。
体調自体は特に問題なく普段通り生活していて、競技もぼちぼち順調に練習もできていたので、
初めて発覚したときより衝撃は大きかったです。
一部の方には直接お伝えしましたが、なかなか全ての方に直接伝えるのが難しいので、
フェイスブックを通してご報告させていただきます。
競技面では会社の方々をはじめ、多くの方々にご支援、ご声援をいただいたり、
一緒に練習や合宿したり、いろいろ挑戦している最中ではありましたが、
しばらくご迷惑、ご心配をおかけします。
気持ち的には社会復帰も競技復帰もするつもりですので、
復帰した際には改めてご支援、ご声援よろしくお願いします」
2015年1月6日。
大阪の長居陸上競技場で1500mを走っている姿に目を止めてから、約半年。
私は、小島の病が再発したことを知った。
【10】
ハイヒールの踵は、アスファルトを踏むたびに甲高い音をたてた。
東雲運河に掛かる橋の上は、人影が少なく、靴音がやけに響く。
私は歩くスピードを速めて、地下鉄有楽町線の辰巳駅を目指した。
湿った風が、スカートを巻き上がるように吹いた。
竜巻のようにうねる風は、どこから私に向かってくるのか分からない。
スカートの裾を抑えると、私の髪の毛を高く巻き上げ、顔に叩きつけてきた。
体を硬くして構えると、風は、台風の目に入ったように突然、止んだ。
時間が止まったような気がした。
勢いよく駆けていく彼の幻影が、私の前に現れた。
ふわりと空中に浮いたサッカーボールが、風に向きを変えられた。
転がるボールを追いかけて、中学生の彼が走っていく。
ボールを蹴るのはうまくなかったが、同級生の誰よりも脚が速かった。
「自分の持ち味は、脚の速さだ」と自信が芽生えた。
高校生の彼が、都道府県対抗の駅伝を走っている。
各都道府県で選抜された選手の中には、彼より圧倒的に速い選手がいた。
外国人選手の走りにも度肝を抜かれ、少しでも近づこうと、熱心に練習するようになった。
進路を考える時期に入り、箱根駅伝を走ってみたくなった。
憧れは、臙脂色に白いWの文字のユニフォーム。志望校は早稲田大学に決めた。
箱根駅伝の第8区。平塚中継所に、風はなかった。
早稲田大学の襷を受け取ると、彼は、勢いよく前の走者を追いかけ始めた。
シード権を手にするには、とにかく順位を上げなくてはならない。
スピードを一段上げて、前の走者を追いかけた。
どんなところを走っていたのか、沿道の景色を全く覚えていない。
前を走っていた選手が一人、目に入った。
その一人を追い抜いたが、どの大学の選手だったのか、ユニフォームの色を覚えていない。
とにかく、「一つ、順位を上げた」と思った。
私の目の前に現れた幻影は、ずっと走っている。
休むことなく、彼は、走り続けている。
初出場の大阪マラソン。
彼は、車いすの選手の最後尾を走っていた。
難関は35キロ過ぎに迎える南港大橋だ。
高低差が20m近くあり、上り下りの勾配がきつい。
上りに差し掛かると、スピードはみるみる落ちた。
漕いでも漕いでも思うように前へ進まず、坂道から転がり落ちないように踏ん張っているだけになった。
腹筋に力を入れ、上半身の力を体の中心に集めた。
両腕を後ろに大きく引きあげ、上から下へハンドリムを押す。
加えた力が車輪をぐっぐっぐっと動かす。
立ちはだかる壁に挑むように、彼は、もう一度、両腕を大きく引き上げた。
レーサーがほんの少し軽くなり、前に進む距離が伸びた。
間髪を入れずに漕ぐと、前に進む距離がまた少し長くなった。
風の流れが変わった。
下り坂に入ると、タイヤが自ら回転し、スピードに乗った。
40キロを過ぎ、ゴールが近づいてきた。
「やっと、戻ってきた。車いす陸上という新たなスタートラインに立てた。勝負の世界に戻ってきたんだ」
涙に濡れた頬を、彼は、ウェアの袖で拭った。
彼の幻影は、どこかへ消えた。
私は、橋の上に一人佇んでいる自分に気がついた。
このまま時が止まってしまえばいい。
そんな願いは、叶わないと分かっている。
分かっていても、分からないことにしたかった。
欄干から身を乗り出して橋の下を覗くと、黒い水面がじっとしていた。
どちらへ向かって流れているのか、分からない。
静かに佇んでいるようにも見えた。
病の再発が発覚して以降、小島は定期的に入院し、抗がん剤の治療を受けていた。
走るために必要な筋肉が落ちることを防ぐため、小島はベッドの上でできる運動を欠かさなかった。
国内トップ選手が走る映像を繰り返し再生し、動きを観察しては、頭の中で自分の体を動かした。
退院すると、すぐにレーサーに乗り、上半身の動きを確認した。
がんの治療と陸上の練習を交互に繰り返す日々が続いた。
体調が大きく崩れたのは、2015年11月の大分国際車いすマラソンでハーフマラソンを完走した後だった。
腰に激痛が生じて動けなくなり、築地のがんセンターに救急搬送された。
「陸上の練習と治療を並行して行うことで、予想以上に自分の身体にダメージが蓄積されていました。
身体の内側では抗がん剤のダメージが、外側では練習の疲れが、ダブルで蓄積していたのだと思います」
小島が近況をフェイスブックに投稿すると、次々とメッセージが寄せられた。
幼稚園から一緒に過ごしてきた近所の幼馴染み、中学・高校時代の友達、
早稲田大学競走部の同期生が、小島の体調を心配し、励ましの言葉を寄せた。
車いすの陸上選手たちは、練習の合間に小島の自宅を訪ねた。
皆、伝えたいことは同じだった。
「戻ってくるのを、待っている」
抗がん剤の治療の効果は芳しくなかった。
未承認の薬を試す治験にも参加したが、副作用が激しく、医師と相談して中断した。
「主治医から呼ばれて、小島君に残されている時間はあと3カ月だと言われました」
2016年5月下旬、美幸さんから送られてきたメッセージは、
読もうとするたびに目が泳いで、直視できなかった。
小島は、右胸に違和感を覚えている。
がんの転移があった。
余命を知らされてはいないが、体の変調を本人が感じていないわけがない。
私は、毎週のように、小島の家を訪ねている。
この橋を渡るのが何度目になるのか、もう、分からなくなった。
今夜、約束した時間に訪ねると、小島はベッドで休んでいた。
ゆっくり体を起こし、車いすに乗り、リビングまで出てきた。
話すことが体の負担にならないか心配すると、小島が「大丈夫です」と言った。
酸素を吸入するため細い管を鼻から入れているが、口調ははっきりしていた。
私は、小島自身が話したいと思っていることを、聞きたかった。
「走ることを通じて、経験できたことがあるし、成長できたんです。
走ることがあったから、今の自分があるんです」。
小島は、言葉を一つひとつ、かみしめるように言った。
「陸上は、僕にとって、人生を彩るものなんです」
黒い瞳が、まっすぐに私を見た。
「今は、また、少し休んでいますけど、車いす陸上という新たな挑戦の舞台を
与えてもらっていますので、次の東京パラリンピックを目指していきたいと思っています」
決意表明のような言葉だった。
私はそれをノートに書き留めて、小島の家を後にした。
なぜ、君は、走るのか。
自分で呼吸をすることが難しくなっても、君は諦めていない。
今は走れなくても、これから再び、走ろうとしている。
走ることで人と出会い、さまざまな経験をし、成長できるからなのか。
走ることが、君の人生を彩ってくれるからなのか。
君の言葉に、嘘はない。それでも、私には分からなかった。
走ることの意味など、本当はもう、どうでもよくなっていた。
走ることに、意味など要らない。
意味など何もなくていい。
ただ、走ること、それだけで十分だ。
私は、小島に走ってほしい。走り続けてほしい。生き続けてほしいだけだ。
湾岸にそびえ立っている高層マンションの窓から、暖かい光が漏れている。
小島が暮らしている部屋の灯りもあるだろう。
水面に映った窓の灯りは、夜空に瞬く星のようだ。
小さな星が一つ、微かな輝きを放っている。
それは、競技場を走っているレーサーのフレームに、太陽の光が反射してできる煌めきに似ていた。
その光の瞬きは、「ふふっ」とこぼれた微笑みにも見えた。
【エピローグ】
隣を走っている黒い車が車線を変更して、前に割り込んできた。
ハンドルを握っている小島が、小さく舌打ちを打った。
助手席に座っている美幸さんが、後ろの座席に座っている私に向かって、声を投げた。
「大阪の将ちゃんの実家に帰省する時、運転を交代しながら行くじゃないですか。
私、しょっちゅう、怒られるんです」
信号が赤に変わり、小島が車を止めた。
スーツ姿の酔っ払いが一人、覚束ない足取りで横断歩道を渡っている。
「えっ?小島君が怒るの?何を怒られるんですか?」
「スピードを上げて、車を飛ばすんですけど。それでも遅いとか、もたもたしているとか。
隣を走っている車と競争する意識があるみたいで、“どうして、今、あの車の前に出ないんだ?”
って怒られるんです」
小島の顔は見えないが、いじわるしたことを告げ口されたような表情をしているに違いない。
「そんなことないやろ」
小島が、小さな声で美幸さんに返す。
美幸さんは、唇を尖らせている。
「小島君、あんまりスピード出すのは危ないし、安全運転が第一だからね」
咎めるような口ぶりで、小島の背中に声をかけると、「ふふっ」と微笑む声が返ってきた。
ワインでほろ酔いになっているのか、美幸さんが小島の告げ口を続ける。
「レースの前はピリピリして、こちらが良かれと思って用意したものが気に入らないと怒るし。
お茶がぬるいとか文句をいいますし、家の中では、本当に、王子みたいな態度なんです」
小島は照れくさそうに、前方の信号を見ている。
「嫁の誕生日なんで、お祝い用のケーキを用意してもらえませんか?」
小島からのメッセージを着信したのは、昨日の夜だった。
三軒茶屋にある創作料理の店で、小島夫妻と私は食事をする約束をしていた。
車いすの人にも入りやすいようバリアフリーを意識した造りで、知人がシェフを務めている。
小島夫妻に以前から紹介しようと思っていた店だった。
小島の病の再発を知ってから、約1カ月。
久しぶりに会った小島は、抗がん剤の副作用で髪の毛が抜けているためにニット帽を被っていたが、
以前と特に変わったところはなかった。
カブやパプリカなどの生野菜を、人参で作られた色鮮やかな黄色いソースでいただき、
牛のヒレ肉を焼いてもらった。
美幸さんは、岡山県で採れたブドウから造られた濃厚な赤ワインを気に入り、何杯かおかわりして飲んだ。
コース料理が終盤になった頃、シェフが店内の灯りを消し、誕生日祝いメッセージを載せたケーキを持って現れた。
ケーキに立てたろうそくの灯が、小島と美幸さんの顔を柔らかい光で包んだ。
シェフも交えて、私と小島が、美幸さんのためにハッピーバースディソングを歌った。
美幸さんがピンク色に染まった頬を膨らませ、息をそっと吹いて、ろうそくの炎を消した。
病の再発が、何を意味するのか。
小島が、これからどうなってしまうのか。
傍に寄り添っている美幸さんは、どうしていくのか。
私には、分からないことばかりだった。
何気ない誕生祝いの光景が、とても貴重で、かけがいのない一瞬になりそうで、怖かった。
「おめでとう」
胸いっぱいに息を吸い、大きな声を出した。
「おめでとう!」
もう一度、繰り返す。小島の黒い瞳が潤んでいるように見えた。
夕方から降っていた小雨は止んでいるが、月は出ていない。
黒い闇が深く、先が見えない夜だった。
「ほら、信号、もうすぐ変わりそうだよ」
美幸さんが声をかけると、小島が思い出したように、ハンドルを握り直した。
鼻から深く息を吸い、ほんの一瞬止めて、ゆっくり吐き出している。
小島は、まっすぐに前を見ている。
どこかで、号砲が鳴った。
【了】
(取材・執筆:河原レイカ)
小島将平氏は、2016年7月15日にご逝去されました。
本作品は、小島将平氏、妻の美幸さんをはじめご家族、
関係者の皆様にお伺いした話をもとに構成しています。
取材にご協力をいただきましたすべての皆様に感謝いたします。
- 投稿タグ
- 企画特集