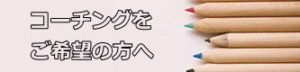【3】
大学を卒業した小島は、不動産関係の企業に就職した。
仕事を始めたその日から、小島は、「同期の社員の中で、一番を目指す」
と決めていた。
誰よりも速く走ることを目指していた男は、同期の誰よりも営業成績を
あげることに目標を定めた。
口下手な自分が営業に向いているとは思えなかったが、とにかく同期に
負けたくない。顧客の求める不動産の条件に耳を傾け、物件を熱心に説明する。
体育会系で鍛えられた礼儀正しさと、熱心な仕事ぶりに結果もついてくる。
数字で示される営業成績は、陸上の自己ベストタイムに似ていた。
成績が伸びると、仕事が面白くなってきた。
社会人2年目を過ぎ、東京・丸ノ内の部署に異動になった。
職場の近くには、皇居がある。堀に沿って走ると1周約5キロのランニング
コースだ。小島は、同僚と一緒にランニングをしようと考えた。
残業が続き、休日出勤が増えていた。毎日、続けている運動はなく、
なまった体に少し刺激を与えたかった。走ることは、気分転換にもなりそう
だった。走ることを趣味の一つとして楽しみたくなった。
着替えをすませると、頭で考えるまでもなく、体が動き始めた。
学生時代に習慣になっていた準備運動は、体に染みついている。
首をほぐすように回し、肩の周りを動かした。アキレス腱をしっかりと伸ばし、
足首をほぐし、シューズの紐が結ばれているのを確かめた。
これから走るのだと思うと、気持ちが引き締まる。気楽にというわけ
にはいかないようだ。
ところが、いざ走ろうとすると、左足に思うように力が入らない。
ふんばりが効かず、力が抜けてしまう。
足の違和感は、それまでに感じたことがないものだった。
整形外科の診療所を受診すると、大学病院を紹介された。
大学病院にいくと、今度はすぐに専門の医療機関への紹介状を渡された。
紹介状の宛先には「がんセンター」と書かれていた。
嫌な予感がした。
様々な検査を重ねるにつれて、胸のざわつきは大きくなっていった。
診断された病名は、骨肉腫。左の骨盤付近に腫瘍ができていた。
「手術室に向かう時、自然と涙があふれてきましたね。
それまで治療を受けていても、辛いとか、悲しいとか、
特に感じたことはなかったんですけど。
その時は、涙が頬をスーッと流れたんです」
小島は、大阪府河内長野市にある中高一貫校に進学し、
中学生の時はサッカー部に入っていた。
ボールを蹴るのは上手くなかったが、他の選手より速く走れた。
自分の持ち味は足の速さだと自信が芽生えた。
高校で陸上部に入り、徐々に頭角を現した。高校2年生の時には、
都道府県対抗の駅伝大会で大阪府代表に選出された。自分よりも
圧倒的に速い選手の走りを見て驚き、もっと速く走りたくなった。
熱心に練習するようになり、努力すればするほど結果もついてきた。
陸上部の顧問をはじめ、学内で知らない生徒からも声を掛けられる
ようになった。「応援されている」「期待されている」と感じると、
走ることはますます楽しくなった。
関東の大学へ進学して、箱根駅伝を走ってみたい。
大学で結果を出せたら、実業団に入ってオリンピックも目指せるかも
しれない。夢は、大きく膨らんだ。
夢を描くことができたのは、脚があったからだ。
自分を支えてきた左脚を、切断しなければならない。
左の骨盤から下すべてを失うのだ。
手術室へ向かう廊下で、小島の頬に熱いものがこぼれた。
私は、テーブルの下で交差していた太腿を外した。
ナイロン製のストッキングで包んだ足を下ろすと、
足の裏からフローリングの冷たさが伝わってくる。
つま先をあげて指を動かしてみると、血のめぐりが良くなり、
じんわり温かくなってきた。重かった足が、ほんの少し軽くなる気がした。
顔を上げると、小島と目があった。
足の感覚を意識していたのを見透かされたようで、胸の奥がチクリとした。
滞ってしまった空気を流してしまおうと思ったのか、小島は一段、明るい声で言った。
「僕は、障害者になった時、生まれ変わったイメージがあったんです」
小島が放った一言は、私には重く響く。
病で闘病した経験も、体の一部を失った経験もない。
そんな私が何を言っても、その場しのぎの言葉になりそうだ。
私は唇を結んだまま、小島に目で返した。
「生まれ変わったとは、どういう意味ですか?」
小島は、脚を切断する手術を受けた病院で、看護師から聞いた話に
惹きつけられた。
「パラリンピックに出場した陸上の選手も、この病院で手術を受けた患者さんだったんですよ」
左脚を切断した後、どうやって生活をしていくのか、
思い描くことができない。職場に戻っても、自分にできる仕事が
あるのかどうか分からない。それなのに、「陸上」という言葉は、
小島をとらえて離さなかった。
「パラリンピック」「陸上」とインターネットで調べてみると、
義足で走っている選手の写真が目に入った。
車いすに乗って走っている選手もいた。
「自分も、走れるかもしれない」
かすかな光が、小島の目の前にある道を照らしだした。
先へ進めば、道がさらに広がっている気がした。
ベッドに横たわると、灰色の天井に鮮やかな景色が映り始めた。
スピードを上げれば上げるほど、前から後ろに流れていく沿道の木立の緑。
競技場に入ると目に飛び込んでくるトラックの擦れた赤。
息をつないでたどり着くゴールラインの白。
「生まれ変わって、新たなチャンスを与えられたと思いました。
チャンスがあるなら、やってみたい。
もう一度、陸上で勝負をしたいと思ったんです」
【4】
その日は朝から曇空が続き、雨が降るのか降らないのか
はっきりしない天気だった。すっきりと晴れていたら、
少し肌寒くても屋外で汗を流そうという気になる。
逆に、土砂降りの雨なら屋外で走るのは無理だと諦めがつく。
どっちつかずの空の下、車いす陸上選手の花岡伸和は、江戸川区の陸上競技場にいた。
「左脚を切断して、車いす陸上をやりたいと言っている人がいる。
見てやってもらえないか」と、車いすテニスの国枝慎吾選手から連絡があった。
国枝は、北京オリンピック日本代表の竹澤健介選手から、早稲田大学競走部時代の
先輩を紹介されたらしい。詳しいことは分からないまま、本人と会うことになり、
陸上競技用車いす(レーサー)を持ってきていた。
2012年、今夏にはロンドンパラリンピックが控えている。
パラリンピックが終わるまでは、自分のトレーニングが第一だから、
他人の練習を見る余裕はない。練習を見てあげるにしても、パラリンピックが
終わった後からになる。それでも構わないという前提だ。
そもそも、これから会う人物が、車いす陸上を本格的に始めるのかどうかも分からない。
とりあえず、レーサーを試してもらうことからだ。
「陸上競技場で待っていたら、到着した車から、小島君が杖をついて降りてきたんです。
まるで、生まれたての小鹿みたいに見えました。体が細くて、壁に沿って伝い歩きを
していたんです。レーサーに乗せたりして、倒れたらどうしようかと心配したくらいです。
えらい、たいへんな人を紹介されてしまった。正直、この人に、スポーツなんてできるの
だろうかと思いました」
小島が近づいてくるのを待ちながら、花岡は空を見上げた。
鼠色の空から小さな雨粒がポツリポツリと落ちている。
雨足は次第に速くなりそうな気配がした。
天候は、ひ弱そうな青年に無理をさせない口実になるかもしれなかった。
「今日は雨だし、レーサーに乗るのはやめておこうか?」
花岡は気遣ったが、小島は競技場へ来る前から決めていた。
「いえ、乗ります」
片足で体を支え、ゆっくりとレーサーの座席に腰を降ろす。
骨盤から下がないため、座った時に左半身が沈み、体が傾く。
右半身の力で体のバランスをとり、車輪の外側についている
ハンドリムに手を添えた。両腕で力いっぱい押してみると、
レーサーがほんの少し前に動いた。
走っているとは言い難い速度だった。自分の脚で走っていた頃は、
こうすれば速くなるというものがあったが、レーサーをどう漕げば
速く走れるのか、全く見当がつかない。
腕の力でハンドリムを押してみるが、力を入れている割には、前に進まなかった。
ちょこん、ちょこんと漕いでいる小さな背中を、花岡が励ました。
「とりあえず、レーサーを漕ぐのに慣れることからだね」
初心者が練習を続けるためには、何か目標があったほうがいい。
小島に出身地を尋ねると、大阪府羽曳野市だと答えた。
「11月の大阪マラソンに車いすの部があるから、
申込みをしておいたらいいんじゃない?」
故郷で開催されるマラソンなら、モチベーションは上がる。
とりあえず出場することを目標に練習してみたらいい。
花岡の提案は、小島が車いす陸上に挑戦するなら応援するという約束だった。
小島は、「車いす陸上の指導してもらうなら、この人しかいない」と決めていた。
「花岡さんとの出会いには、縁を感じたんです。
花岡さんも大阪の出身で、ご実家は、僕がよく知っている地域にあるんです。
もしかしたら、僕は、高校生だった頃に、花岡さんとすれ違ったことがあった
かもしれない。もちろん、その時はお互いに知らなかったわけですけど、
車いす陸上を始めると決めたら、引き寄せられるように、すぐに出会えた。
不思議な縁だと思いました」
⇒ つづく
(取材・撮影:河原レイカ)
- 投稿タグ
- 企画特集