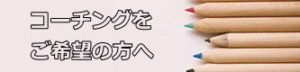【1】
「切断する前までに、僕は、普通の人の一生分くらい、自分の脚を使っていたと思うんです」
東京・江東区にある公団住宅の一室。
リビングに置かれた木製の四角いテーブルを挟んで、私は、小島将平の話を聞いていた。
冷たいグリーンティーが入ったグラスは、側面にびっしり汗をかいている。
小さな水滴が少しずつ下へ落ち、一つの筋となって流れていった。コースターの上に
落ちた滴は、グラスの底面を縁どるように染みをつくっている。
小島は、乾いた喉を潤し、メモをとっている私をチラリと見た。
一生分使ったとしても、脚を失うことに見合う理由にはならない。
そのことは、小島も私も当然、知っている。分かっていることはあえて確認
しないというのが、暗黙の了解だ。私は、それに乗った。
「たしかに、小島君なら、学生時代に地球を何周かするくらい走っていた
かもしれないですね」
人差し指で空中に円を描いて、地球の周りを赤道に沿って走っていく
イメージを表すと、小島は丸い目をくるりと回して微笑んだ。
「オリンピックのマラソン選手なら、何周もですね。
僕の場合は、どのくらいだろう」
「少なくとも一周はしているでしょう?」
「そうですねぇ。一周は、走っているかもしれない」
私は、“地球一周”とノートにペンを走らせ、文字の周りをぐるりと
丸で囲んだ。描いた円は、均等に割られているノートの罫線の間から
はみ出している。しっかり書き留めたからといって、小島が失ったもの
を取り戻せるわけではないが、小島の脚の存在を記録しておくことには
なるだろう。
小島の口元から「ふふっ」と声にならない微笑みが漏れた。
私は慌てて顔を上げたが、その微笑みはどこかへ消えていた。
感情を隠しているわけではないが、小島の喜怒哀楽はいつもささやかで、
私がとらえる前に消えてしまう。
照れくさくなったのか、小島は車いすのハンドリムに手を添えて数センチ前へ
押し出している。車輪はにじり寄るように進み、小島とテーブルの間が狭くなった。
「地球を一周するくらいたくさん走った。普通の人の一生分は使ったん
だからと考えて、切断を受け入れたんですか?」
テーブルの縁を見ていた小島が、顔を上げた。
「そんなはずはない」と分かっている。
分かっていることは言わないのが大人の礼儀だが、なぜか、私は口に
してしまった。胸にしまっておけばよい質問を外に出してしまったのだ。
もう元には戻せない。
俯いてしまいたい気持ちに抗って小島の顔を覗くと、黒い瞳がまっすぐに
私を見ていた。
「高校や大学の頃だったら、もう少し違う気持ちだったかもしれません。
僕は、大学で陸上に区切りをつけていましたし、社会人になって2年経って
いたので、脚の切断をそんなふうに考えられたのかもしれません。
走ることへのこだわりには、もう区切りをつけることができていたんです。
それよりも、とにかく、生きたいと思って。生きるためには治療をする
しかない。生きるためには切断しなくてはならないと思ったんです」
【2】
どっと笑い声が沸き、黄色い羽織と袴を身に着けたお笑い芸人が顔を
ゆがめている。白いクリームが乗ったケーキに埋められていた顔をあげ、
大げさに驚いてみせている。
この時が注目を集めるチャンスだと思っているのか、顔がしっかり映る
ようにテレビカメラに近づいて声を張り上げた。
リモコンを引き寄せてチャンネルを変えると、テレビ画面には、急勾配
の坂道を懸命に走っている学生の姿が映し出された。
「箱根だ」
私は、こたつの中に投げ出した足を引き寄せて、姿勢を正した。
毎年1月2日、3日の2日間にかけて開催される箱根駅伝は、日本の正月
の風物詩になっている。箱根駅伝は、東京・大手町から箱根・芦ノ湖
までの往路5区間、復路5区間を各チーム10人の選手で襷をつなぐ。
実況のアナウンサーが、走者の家族のエピソードを紹介している。
母子家庭で育った走者は、母親に箱根を走る姿を見せることを目標に
してきた。沿道のどこかにいる母親は、走者が近づいてくるのを今か
今かと待っている。
故障のために走れなくなり、今はマネージャーとなってチームを支え
ている学生がいる。
大きなスポーツタオルを片手に中継地点で待っている彼は、心の中で
走者とともに走っている。アナウンサーが語る声に耳を傾けていると、
両親やチームメイトが走者を見守っている姿が頭の中に浮かんでくる。
タン、タン、タンとリズムよく走っていく走者の足取りに、心が弾む。
額に皺を寄せている走者の表情が目に入り、体の不調ではないかと心配する。
家族でも、友達でも、母校の走者でもないのに、身近な人が走っている
気がしてきた。
「頑張れ、もう少しで中継地点だ」
テレビの前で、私はつぶやいた。
あの年も、箱根駅伝を見ていた。箱根駅伝の見どころの一つ、
シード権争いを見逃すはずがない。
出会う前の小島将平が、前の走者を追っている姿を見ていたはずだ。
私は、シード権を求めて必死に走っている小島を見ながら、何をつぶやいた
だろうか。
箱根の常連となっている早稲田大学競走部には、全国から優秀な選手
が集まる。長距離選手は約40名。皆、箱根の走者を目指しているが、
実際に襷をかけて走ることができる選手はごく一部だ。
学生時代の小島は「走りが遅くなる」と思う行動をすべて、日常生活
から除外していた。食事の時、白飯をもう一膳食べられると思っても、
太りすぎてはタイムが遅くなるとおかわりするのを控えた。インスタント
食品も体に良くないと、口にしない。外出といえば、学生寮の近くの
ドラッグストアに日用品を買いにいく程度。授業に出ているか、陸上の
練習をしているか二つに一つで、大学と学生寮を往復する毎日だった。
「大学生の時は、速く走ることだけをひたすら追求していました。
練習を少しでも休んだら、すぐ遅くなってしまうという気持ちで走って
いたんです」
箱根の走者10名に入れるかどうか。競走部内での走者争いは、
箱根駅伝の直前12月末まで続く。実力が抜き出ている選手や実績のある
選手はおおむね6名程度。残り4名に入るための争いは熾烈を極める。
大学2年生の小島は、ボーダーラインにいた。2年生の自分にチャンス
が与えられるか、実績のある4年生の選手に任せられるか。監督やコーチ
の考え一つで起用されるかどうかが決まる。大晦日が間近に迫った日、
小島はコーチから声をかけられた。
「今回の箱根は、いくから」
全身がキュッと引き締まった。
小島は、第82回箱根駅伝の第8区走者に選ばれた。
「家族が中継地点で応援をしてくれていたらしいんですけど、
まったく気がつきませんでした。走っている間も、沿道の景色を見ている
余裕はなく、どんなところを走っていたのか全く覚えていません。
とにかく、順位を一つでも上げなくてはいけないと思っていました」
箱根の第8区は、平塚から戸塚までの21.5キロ。
復路の半ば、総合順位やシード権の行方がみえてくる区間だ。
臙脂色に白い「W」の文字が輝くユニフォームを身につけ、小島は、
平塚中継所で待っていた。往路9位だった早稲田は順位を落とし、
シード権争いの中にいる。襷を受けた小島は、勢いよく走り始めた。
小島は、すぐに前を走っていた選手を1人捉えた。どの大学の選手
を抜いたのか、ユニフォームの色を覚えてはいない。
とにかく「1つ順位を上げた」と思った。
しかし、後ろから前へ上がってきた選手に追いつかれた。
その選手に離されてはいけないと、しばらく並走して粘ったが、
15キロ付近で差がつき始める。圧倒的に力が違うという感じは
しなかったが、じりじりと背中が遠くなった。
小島の成績は、区間順位11位。
「チームに貢献するためには、もっと自分が速くならなければいけない」
箱根を走るという夢は叶った。
夢が現実になると、箱根に寄せる思いはいっそう強くなった。
「大学生活の4年間は、箱根駅伝だけに懸けていたんです」
小島は、かみしめるように言った。
「陸上の他には何もありませんでした。
僕には、陸上だけ、走ることだけしかありませんでした」
箱根駅伝の話をした時の小島は、記憶の中に大学生の自分を探していたのか、
どこか遠くを見ていた。
学生寮の食卓で、もう一膳、おかわりするのを控えた時に眺めた
茶碗の底を思い出していたのだろうか。
寒い冬の朝、湯につけてほぐしていた足の強張りを思い出していたのか。
陸上競技場で、後輩たちが気持ちよさそうに走っていく姿を、トラックの脇から
眺めていたことを思い出していたのか。
「自分には、陸上だけだ」
「自分には、走ることしかない」と思っていた。
その思いは、足が悲鳴をあげるまで、小島を追い込んでしまった。
アキレス腱の周囲炎だと分かったのは、箱根を走ってから、ひと月後のことだった。
それから、脚の状態を気にしながら走る日々が続いた。
早稲田大学の襷をかけて箱根を走るチャンスは、二度と訪れなかった。
つづく
取材・撮影:河原レイカ
- 投稿タグ
- 企画特集