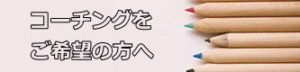パラ陸上・車いす男子T54クラスには、2020年東京パラリンピックでの活躍を期待されている二人の“トモキ”がいる。
一人は、短距離(100m、200m)をメイン種目とする生馬知季(いこま・ともき)選手(25歳、グロップサンセリテ WORLD-AC所属))。もう一人は、中長距離をメインとする鈴木朋樹(すずき・ともき)選手(23歳、トヨタ自動車所属)だ。今シーズンの主な大会を終えた今、二人の“トモキ”は、自分自身をどう捉え、何を考えているのだろうか。
■短距離の生馬
短距離100m、200mをメイン種目としている生馬知季選手は、日本人選手のなかでは比較的上半身が大きく、上腕が太い。その腕でスタートから序盤に、競技用の車いす(レーサー)のハンドリムをぐいぐい押して、前へ出る。
「100m14秒台を指標にして、昨年からトレーニングを積んできました。特に取り組んできたのは、スタートの強化です。スタートからいかに早い段階で初速に乗せられるか。フォームを考え、体幹を強化してきました」
トラック種目のうち800m以上の中長距離は、競い合う選手の集団のどの位置につけるか、どの地点で集団から前へ抜け出すかなどの駆け引きがあり、勝負には速さだけではない要素が絡む。しかし、短距離は、そうした要素が要らず、いかに速く走れるか、最高速度(トップスピード)の勝負になる。他の誰よりも速度を出して、ゴールまで駆け抜けた者が勝者だ。
生馬は、今年7月に英国ロンドンで開催された世界パラ陸上競技選手権大会ロンドン2017(世界パラ陸上)に日本代表として出場した。2009年に東京で開催されたアジアユースパラ競技大会で日本代表に選ばれた経験はあったが、世界の舞台に立ったのは今年の世界パラ陸上が初めて。結果は100mで決勝に進出し8位、200mは予選敗退だった。
「世界選手権の100mでは、スタートから30mくらいまでは、トップレベルの選手たちに引けを取らない走りができたと思います。ただ、根本的なトップスピードは、トップの選手との間に決定的な差があります。50mを通過して以降は、スピードの伸びにも実力差があります」。
生馬の100mのトップスピードは、調子が良い時で時速33キロ。これに対し、世界トップレベルの選手は36キロ前後を出し、そのスピードを保ったままゴールまで走っていく。スタートからトップスピードに乗せるまでの時間も短い。
スピードを縦軸に、時間を横軸にとったグラフを頭に描くなら、グラフの左下端のゼロ地点から右肩上がりの線が一気に立ち上がり、選手が出せるトップスピードの位置まで昇った後は、その高さを保ったまま時間の進行とともにゴールを通過するまで進んでいくイメージだ。理屈は簡単だが、生馬は、これを自らの身体の動きでどのように実現しようとしているのだろうか。
「走りについて参考にしている選手がいるのですか?」と尋ねると、生馬は、2016年のリオ・パラリンピック100mの金メダリストで世界記録(13秒63)を持つフィンランドのレオペッカ選手(TAHTI Leo Pekka)を挙げた。
「レオペッカ選手は、上半身の上下運動を抑えた動きで、レーサーをスピードに乗せていきます。YOUTUBEの動画で走りを見て、短距離でスピードを出すには効率のいいフォームだと思いました。ただ、レオペッカ選手と僕とはちょうど真逆です。僕は、ピッチよりもストロークで漕いでいる選手です。世界選手権の時には、まだ、速いピッチで漕ぐフォームをつくれていませんでした」
車椅子の選手は、レーサーの車輪の外側に付いているハンドリムを両腕で漕ぐようにして走る。ピッチとは、一定時間内に押す回数。スピードを上げるには、ピッチを増やすほか、一回の漕ぎ(ストローク)を工夫して加速する方法がある。
生馬は、ロンドンの世界選手権を終えて帰国した後、所属チームの監督である松永仁志選手(男子T53クラス、リオ・パラリンピック日本代表)に相談しながら、ピッチを活かした走りができるよう自身のフォームの改善に取り組んだ。
具体的には、レーサーを漕ぐ際に押すハンドリムを、爪の高さが低いものに変更。これにより、車輪の外側を覆っているディスクホイールと、その表面に円周状に付いているハンドリムとの隙間が狭くなった。生馬は手にソフトグローブを嵌めて漕いでいるが、爪の高さが低いハンドリムに手を添えるとディスクホイールにペタッと着くような感覚があり、手首が安定するという。
もう一つの変更は、座席に敷いているスポンジを一枚増やしたことだ。レーサーを漕ぐ際に、選手たちは前傾姿勢をとるが、お尻の位置を少し高くしたことで、上半身の前傾をしやすくした。これにより、以前よりもピッチが改善した。
世界パラ陸上以降の取り組みの成果が見えたのは、9月に福島市で開催されたジャパンパラ陸上競技大会の200mだった。記録は25.87の自己ベスト。永尾嘉章選手が持つ日本記録25秒80に迫る記録だった。それまでの生馬の自己ベストは、今年5月の大分パラ陸上競技大会で出した25秒99だった。
生馬によると、大分パラ陸上の200mと、ジャパンパラ陸上の200mのトップスピードは変わらなかった。同じ距離を、同じトップスピードで走って、結果としてタイムが縮まっている。これは、スタートからより早い段階でトップスピードに乗せ、その速度を維持して走ることができた成果だといえる。
「走りの中身が変わってきたと思います。ジャパンパラで、それを自分でも実感できました」。
生馬はピッチよりもストロークで漕ぐタイプだが、そのストロークを、まだ十分には活かしきれていない。世界のトップ選手と肩を並べて戦うためには、トップスピードをさらに上げることや、加速の伸びにつながる動きをつくることなど課題はまだいくつかある。
しかし、生馬は今、自分自身に変化を起こそうとしている。彼は、ジャパンパラでつかんだ小さな変化を大きく膨らませていくことができるだろうか。そして、それを走りの進化と言えるものにつなげることができるだろうか。
2020年東京オリンピック・パラリンピックまで約1000日となり、カウントダウンが始まった今、世界の舞台にようやく出た若芽が一つ、勢いよく上へ上へと伸びようとしている。そんな気配を、私は感じている。
【取材・撮影 河原レイカ】
- 投稿タグ
- 企画特集