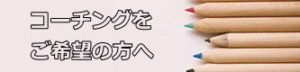多摩川の水の流れを見下ろすことができる公園の駐車場。
河川敷では少年野球チームの練習が始まっている。
少年たちを送ってきた家族か関係者の車なのか、
ファミリー用の自家用車が並び、駐車場は7割程度埋まっていた。
例年より早い梅雨明けとなり、午前9時だというのに、
日焼け止めを塗った肌が太陽にじりじり焼かれている。
「おはようございまぁーす!」
車椅子に乗った女の子が、こちらを向いて元気な声で挨拶している。
家族や介助者に連れられて子どもたちが集まってきた。
障害者専門のスポーツ教室を実施しているNPO法人アダプティブワールドの自転車教室。
この日の参加者は5名。4歳から20代まで年齢層は幅広い。
脳性マヒなどの障害があり、車いすを自分で漕ぐことが難しい子もいる。
子どもたちの前には、大きさがさまざまな自転車・三輪車が並べられていた。
よく見ると、ハンドルやペダル、チェーンの位置が、一般的な自転車・三輪車とは違う。
アダプティブワールドの自転車教室では、手で漕ぐ自転車「ハンドサイクル」、
手漕ぎと足漕ぎで連動して動く三輪車「エイムトライク」、
つかまり立ちができれば乗れる三輪自転車「リハトライク」を体験できる。
「じゃあ、どんどん乗ってみましょう!」
代表の齊藤直さんが声をかける。子どもたちは保護者に促されながら、乗りたい自転車を選んだ。
体育大学の学生と専門学校でリハビリテーションを学んでいる学生が、スタッフの役割を担う。
参加者が自転車から落ちないようにベルトの具合などを確認する。
下肢を伸ばして乗るハンドサイクルを選んだ青年は、準備が整うや否や、胸の前でハンドルをぐるりと回した。
その一漕ぎが、後方についている2つの車輪に伝わり、ハンドサイクルがぐぐぐっと動き出す。
手元のハンドルの回転数が上がり、車体はアスファルトの上をスーッと滑るように走り始めた。
一人は、手漕ぎで進むハンドサイクルに乗って走りだし、また一人は、手と足の両方で漕ぐ三輪車に乗った。
200~300mほどの距離を行って帰ってくる。齊藤さんは参加者それぞれの状態や様子を見ながら、時々、声を掛けている。
「アダプティブワールドの教室では、“できた”という経験をしてもらうように心掛けています。
“できない”という経験は、“もう、やらない”につながってしまう。“できた”という経験があると、
次にこうしてみようという意欲が出てくる。
まず、“できた”を経験してもらい、次のステップに挑戦する意欲を引き出すことを大切にしています」
この日は、母親に連れられて、4歳の男の子が参加していた。
最初は、足だけで漕ぐ三輪車に乗ったがうまく漕げず、前に進むことができなかった。
そこで、齊藤さんは、手漕ぎと足漕ぎが連動して動く三輪車に乗ってみるよう勧めた。
手漕ぎ足漕ぎ両方で動く三輪車は、手漕ぎが加わるぶん、足で漕ぐ力が小さくても前に進む。
男の子は、自分の手足の力で三輪車が前進すると、目の色が変わった。
「できた!」という手ごたえが4歳児の心に火をつけた。
手と足の動きが力強くなり、三輪車がぐいぐいと動いた。
手漕ぎ足漕ぎ連動の三輪車に慣れたところで、齊藤さんに促され、再び、足漕ぎだけの三輪車に挑戦した。
今度は、ペダルを踏む足の運びが上手くいき、三輪車が動き出した。
「まず、手漕ぎと足漕ぎの三輪車に乗って、体に足の漕ぎ方を覚えさせるんです。
体が漕ぎ方を覚えたところで、今度は、足漕ぎだけの三輪車に挑戦してもらいました。
男の子は、つかまり立ちができていましたし、ぎこちないけれど、自分の足で歩くことができます。
体の機能的には、足漕ぎの三輪車に乗れると分かっていました。
それで、手漕ぎ足漕ぎの三輪車で足の漕ぎ方の経験型学習をしてもらってから、
足漕ぎのみの三輪車に乗ってもらいました。
僕たちは、障害のあるお子さんの身体と、その機能、それから自転車・三輪車など道具の性能を見て、
どうやったら子どもの能力を引き出せるかを考えながら指導しています」
■日本では、障害者の生活の中にスポーツが根付いていない
齊藤さんは、日本体育大学在学中に、全米障害者スポーツセンターなど米国NPO法人を訪ね、衝撃を受けた。
2000年頃、当時の日本では、車いすの人のスポーツといえば、車いすバスケットボールか、車いすマラソン。
スポーツをしている障害者は、パラリンピック出場などを目指し、本気で取り組んでいる人たちが多かった。
これに対し、米国では、障害者があっても自転車に乗り、「ちょっと、家族と一緒に公園まで出かけてくる」
と言って、気軽に楽しんでいる人たちがいた。
「日本では、障害者のスポーツ=競技のイメージだったです。でも、米国では、障害があっても、生活の中にスポーツがある。
レクリエーションとしてのスポーツを楽しんでいて、これは、日本にはないと思ったんです」
大学を卒業した齊藤さんは、2002年に、障害者専門のスポーツ指導のプロ集団としてアダプティブワールドを立ち上げた。
米国から中古のハンドサイクルを2台購入し、04年から自転車教室を始めた。
現在、アダプティブワールドの教室や個別指導には、全国各地から参加がある。
遠方から飛行機で来る人もいる。
齊藤さんによると、特別支援学校にも体育の授業はあるが、安全を重視するため、
プールの時間なのに泳がなかったり、車いすから降りずに座ったままで過ごすケースがあるという。
「障害があっても、運動をさせたい」「子どもの運動能力を引き出したい」という希望を持つ保護者は、
運動できる場や指導してくれる人を探すなかで、アダプティブワールドの教室に辿りつくのかもしれない。
遠方からも参加者があるのは、障害者専門のスポーツ教室が身近にないからだろう。
「僕は、体育の先生は、リハビリのことを学ぶべきだと思っています。
そして、リハビリの先生は、体育についてもっと学ぶべきです。
理論で“できない”と位置づけるのは簡単なんだけど、“どうやったら、できるか”を考えることが重要です。
例えば、競泳の4泳法だけが、泳ぎじゃない。プールのここからあそこまで行けたら、すごいじゃないですか。
この子は障害があるのだから無理だという考えを、どれだけ排除していけるか。
浮き具を変えたり、スカーリング(手で水をとらえる動作)の方法を変えたりして、
泳げる方法を考えることが重要だと思うんです。
でも、特別支援学校の先生方が、そうした指導法を学べる学校内研修はありません。
体育とリハビリの狭間にある領域なんです。僕は、その狭間の領域こそ、必要なものだと思っています」
アダプティブワールドは、これまで積みあげてきた障害者への運動指導のノウハウを、
特別支援学校の先生に教える事業を2017年から始めた。
齊藤さんは、子どもたちの“できる”を引き出せる体育の指導者を増やしていきたいと考えている。
■2020年、末端の施設に変わってほしい
2020年の東京パラリンピック開催が決まり、障害者スポーツの普及や支援の施策が進められている。
健常者のスポーツと同様に、障害者スポーツで競技力の高いアスリートを輩出するには、
競技人口を増やすことが不可欠だろう。競技人口のピラミッドの裾野を広げることが必要になる。
だから、齊藤さんが取り組んでいる活動にも追い風が吹いているかというと、そうではない。
「始めた頃と今と比べて、何も、変わらないですね。
2020年で何かが変わると期待している人にはショックな言い方になるかもしれないけれど、
僕は2020年が来ても何も変わらないと考えています。
パラリンピックのアスリートのための施設を作ることも重要かもしれないけど、変えるべきは末端の施設だと思います。
例えば、今、僕らが、公共のプールに行って、障害のある子に声を掛けていると、
施設の管理者から“指導はしないでください”と言われてしまいます。
そういうルール、規則だからと言われます。
僕らが活動したいと考えても、使わせてもらえる公共施設はなかなかないんです。
ビジネスとして考えた時、障害者スポーツは食えないと言われていて、たしかに難しいところはあります。
でも、お金の問題よりも、環境の問題です。公共の施設を使わせてもらえないなど環境に阻まれることが大きいです」
■100人いたら100とおりの指導を
自転車教室の終盤、参加者一人ひとりが一定の距離を走り、タイムを測ることになった。
一番速いのは誰かを決めるレースではない。
それぞれが自分の予想タイムを申告し、実際に走ったタイムが予想に一番近かった人が優勝する。
他人の速さと比べずに、競い合える方法だ。障害の種類や程度に差があっても平等で、一緒に楽しめる。
保護者が子どもの能力を引き出したいと考えた時、どんなことを心掛けたらよいだろうか。
齊藤さんに尋ねると、次のような答えが返ってきた。
例えば、「今日は、ハンドサイクルに乗れたけれど、うちの子は、普通の三輪車には乗れない。
乗れるようにならないのですか?」と言う親御さんがいたら、
僕は、「普通の三輪車に乗る必要は、何ですか?」と尋ねます。
「他の子が乗っているから」みたいなことを言われるんですけど、
でも、「結果的に、お父さん、お母さんが、やりたいことは何ですか?」と聞いて紐解いていくと、
「子どもと一緒に公園にいきたい」ということだったりします。
それなら、その子が乗れる三輪車で実現できると気が付かれます。
「泳げるようになりたい」という親御さんの希望を紐解いていくと、
「旅行に行った時に、家族で海に入れるようになりたい」とか、
「一緒にプールに行けるようなりたい」とか、そういう具体的なことがでてきます。
他の子と比べて同じの方法やルールを当てはめないことが重要だと思います。
健常者だって、100人いたら100とおりじゃないですか。
希望を叶えるために100とおりの方法があっていい。
そういうことを理解して、運動を指導できる人がいたら、
もっと日本でアスリートが生まれるし、運動好きが生まれると思っています」
(取材・撮影:河原レイカ)
- 投稿タグ
- 企画特集