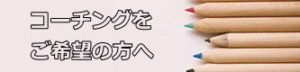東京大学の駒場キャンパスは、京王井の頭線の駒場東大前駅を降りると、すぐ目の前にあった。
同じ電車から下車した数十人の乗客は、大学生か教員だったのだろう。
駅から正門まで100mもない真っすぐな道を、迷いなく進んでいく。
私は、駅の構内を出るとすぐにスマートフォンで東大のホームページを開き、目の前の門が駒場キャンパスの正門であることを確かめた。
地図でみると、門の先にはいくつか建物が立っているはずだが、深緑色の樹木に隠されていてよく見えない。
鞄の中には、中澤教授に送付した取材依頼書が入っている。
依頼書に自分が知りたいことを列記すると、NHKのラジオ番組の「夏休み子ども電話相談室」で寄せられる質問のようになった。
幼稚な内容かもしれないが、私にとっては、どれも大事な質問だ。
質問に答えてもらえるかどうかは、まったく分からない。
取材を断られても仕方がないと思っていたが、中澤教授からはすぐに取材を了承する返信が届いた。
短い返信だったが、取材について前向きに受けていただいている印象があった。
「私の話がお役に立てるかどうか分かりませんが…」
4人掛けのテーブルに斜交いに座っている中澤教授の一言で、私の肩の力がすっと抜けた。
やはり、少し緊張していたようだ。
両肩を意識してほんの少し後ろへ引くと、縮んでいた胸がひらく。
鼻からすーっと細く息を吸い込み、肺の奥まで入れて横隔膜を下げてみた。
足りなかった酸素が補充され、小走りだった鼓動が歩くペースに戻っていく。
案内された部屋は、ホワイトボードとテーブルが置かれていたが、それ以外の物は少なく、がらんとしている。
ラジオ体操程度なら十分にできる広さだ。何かを測定するために使われている部屋なのかもしれない。
私は、高次脳機能障害の陸上選手を取材していること、脳の機能について関心を持ったこと、そして「パラリンピックブレイン」の文献を見つけたことを伝えた。
椅子に深く腰を掛けて、私の話に耳を傾けていた中澤教授は、言葉を一つひとつ慎重に選びながら、話を始めた。
「“パラリンピックブレイン”という言葉は、パラアスリートの脳について積極的に発信していこうと思っているときに浮かんだ言葉です。
以前に読んでいた本のなかに、“オリンピックブレイン”という言葉が使われていたんです。
それが印象に残っていて、“オリンピックブレイン”があるなら、私の研究の対象は“パラリンピックブレイン”だと思ったんです」
中澤教授が、障害のあるスポーツ選手の脳について積極的に発信したいと考えたのは、理由があった。
障害という言葉を聞くと、何かを失うというイメージを持つのが一般的だ。
しかし、中澤教授は、脳の研究を続けるなかで、障害をもつことは何かを失うばかりではなく、何かを得る側面もあるのではないかと考えるようになったという。
「例えば、脊髄を損傷して下肢の機能を失った方がいるとします。その方は歩けなくなり、車いすを使わなければなりません。足が使えませんので、日常生活の中での移動はもちろん、さまざまな動きをする際に、嫌でも手を使わざるを得なくなります。このような方の上肢の能力を測定してみると、健常者の上肢の能力よりも高くなることがあるんです。
視覚障害者の場合を考えてみても、目は見えませんが、耳の能力が健常者以上に発達する場合があるんです。
“パラリンピックブレイン”の寄稿では、水泳の選手と陸上の走り幅跳びの選手の研究について書いています。水泳の選手は、水泳特有の運動に脳が適応しています。運動することによって、脳がその運動に適応するように変化する可能性があることを示しています」
(取材・執筆:河原レイカ)
- 投稿タグ
- 企画特集