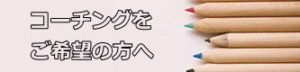パラスポ!インタビュー
この人に聞く
一般社団法人コ・イノベーション研究所
代表理事・橋本大佑さん
はじめに
2020年、日本でパラリンピックが開催される。
パラリンピックは、4年に1度、オリンピックと同じ都市で開催される障害者スポーツの世界最高峰の大会だ。
2020年に向けて競技場の建築や整備が進められ、選手の強化・育成に多額の予算がつき、若手選手の発掘事業も開催されている。
障害者スポーツを取材するメディアの数は格段に増え、テレビや新聞、ウェブサイトなどで取り上げられる機会が以前より増えた。
有力選手が大手企業にアスリート雇用されることも珍しくない。
これから2020年までを想像すると、障害者スポーツの認知がさらに向上し、スポーツをする障害者が増え、選手を支援する体制も充実するだろう。
選手を応援する人も増え、観戦を楽しみに競技場へファンが詰めかけるかもしれない。
パラリンピックをきっかけに、障害者全般に対する理解も広がる。
「スポーツをしたい」だけでなく、「働きたい」「学びたい」などの希望も障害を理由に制限されることがなくなる。
「障害がある人も、ない人も、同じ」だと誰もが感じられる世の中になっている。
そんな未来を思い描こうとしたが、私の頭の中でストップがかかった。
この人に聞く理由
「義足の選手がCMに出ているのは、見たことがある」「パラリンピックの競技、テレビで紹介されていたね」という人は増えているだろう。
しかし、白杖を手にした人が街中で立ち止まり、方向を確かめる様子をしていたらどうだろうか。
通りかかった人が声をかけ、困りごとを尋ねて、必要なサポートをするのが当たり前になっているだろうか。
企業の人材募集に、筆談でやりとりしなければならない人が応募してきたら、どうだろうか。
仕事を処理する能力があれば、すんなり採用されるだろうか。
2020年の東京パラリンピックは、障害者をとりまく環境に、どれほどの影響を与えるのか。
気になった私は、手がかりになる資料を探しているなかで、1冊のテキストに出会った。
一般社団法人コ・イノベーション研究所(COIL)の橋本大佑(はしもと・だいすけ)さんが監修した『ロンドン大会は成功だったのか?東京大会に向けて今から取り組むべきことは何かを考える』だ。
このテキストでは、2012年のロンドンパラリンピック(ロンドン大会)を通して、障害者に対する態度や障害者のスポーツ参加について「改善した」という政府報告と、「悪化した」とする民間調査があることに触れている。
また、ロンドン大会の調査事例を踏まえて、2020年の東京大会が目指す共生社会とはどのようなものか、その実現に向けて必要なものについて解説している。
ドイツで障害者スポーツの指導法を学んだ経験を持ち、体験型学習の提案や研修、コンサルタントなどの事業を行っている橋本さんに、2020年の東京パラリンピックと障害者理解の推進について話を聞いた。
【聞き手】
まず、2020年の東京パラリンピック開催について伺います。
東京大会が目指すものは何か。
また、その目標の実現に向けて、何が必要だとお考えでしょうか。
【橋本】
東京パラリンピックが目指すものについては、政府の「東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部」の下に設置された「ユニバーサルデザイン2020関係閣僚会議」が2017年2月に「ユニバーサルデザイン2020行動計画」をまとめています。
この行動計画では、東京パラリンピックを契機として実現を目指す共生社会の考え方を示しています。
また、共生社会の実現に向けた施策として、「心のバリアフリー」と「ユニバーサルデザインの街づくり」を進めることが盛り込まれています。
【聞き手】
「バリアフリー」というと、街の中や公共の建物などで、車いすの方が移動できるようにスロープを設けたり、視覚障害のある方のために点字ブロックを備えていることが思い浮かびます。
ハード面でのバリア(障壁)をなくす「バリアフリー」ですね。
一方、「心のバリアフリー」というと、心の中の障壁をなくすことかと思うのですが、少しイメージが沸きにくい気がしました。
「ユニバーサルデザイン行動計画」では、「心のバリアフリー」について、「様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合うこと」とされています。
そのための行動のポイントとして、
(1)障害のある人への社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるという「障害の社会モデル」を理解すること。
(2)障害のある人(及びその家族)への差別(不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供)を行わないよう徹底すること。
(3)自分とは異なる条件を持つ多様な他者とコミュニケーションを取る力を養い、すべての人が抱える困難や痛みを想像し共感する力を培うこと。が挙げられていました。
2つ目の差別をしないこと、3つ目のコミュニケーションや共感することは理解できたのですが、1つ目の「障害の社会モデル」はあまり馴染みがないもののように思います。
【橋本】
「障害の社会モデル」とは、障害者が何らかの機会を損失した時、その原因を個人ではなく、社会の側にあるとする考え方です。
「障害の社会モデル」では、障害は、個人の心身の機能の障害と社会的な障壁の両方から創られるものであり、その障壁を取り除くのは社会の責務としています。
例えば、飲食店の入り口に段差があり、車いすの方がお店に入れないような状態がある時、「車いすだから、お店に入れない」のではなく、「車いすの方もお店に入れるように配慮されている社会になっていないからだ」と考えていくのが「障害の社会モデル」です。
「障害の社会モデル」を理解することは、障害のある方が経験する社会的な障壁に気づいて、解消を目指していこうとするものです。
私個人は、「障害者スポーツを、障害者の社会参加のツールとしてどう活用できるか」というテーマをもとに活動してきました。
これは、2020年の東京パラリンピック開催に関わらず、取り組んできたものです。
そういう立場から2020年に向けて様々な施策が進められているのを見て、最初はすごく違和感がありました。
ただ、その違和感が何なのか、なかなか言葉にできなかったのです。
【聞き手】
私自身は、2004年のアテネパラリンピックをきっかけに、障害者スポーツに関心を持ち、取材を続けてきました。
2013年に2020年の東京パラリンピック開催が決定して以降、取材するメディアが増えました。
テレビや広告でも障害者アスリートが登場することが珍しくありませんし、障害者スポーツのイベントも増えました。
それは良いことだと思っているのですが、時折、少し引いた目で見ることがあり、「一過性のお祭りで終わってしまうのではないか」「2020年の後に、一体、何が残るのだろうか」と考えてしまうことがあるんです。
なぜ、そう思うのか。私自身は、よく分かりません。
橋本さんは、ご自身の違和感の理由をつきとめられたのでしょうか。
【橋本】
2016年に、私が代表理事を務めている一般社団法人コ・イノベーション研究所が、内閣官房の委託事業「オリンピック・パラリンピック基本方針推進調査(ユニバーサルデザインの社会づくりに向けた調査)試行プロジェクト」を実施することになりました。
この委託事業の成果物として、『「心のバリアフリー」教育・研修プログラムに必要な評価基準作成に関する提言書』をまとめています。
これは、「心のバリアフリー」教育・研修を実現するには、どのような評価基準が必要かを政府に提言したものです。
提言書をまとめるために、障害者スポーツやパラリンピック、共生社会に関する調査研究をすることができました。
それで、私自身が感じていた2020年の東京パラリンピックに対する違和感が構造的にどういうことか把握できたんです。
【聞き手】
橋本さんが感じていた2020年に対する違和感の理由が構造的に理解できたというのは、どういうことですか?
【橋本】
パラリンピックの歴史を振り返ると、英国のストーク・マンデビル病院で、障害者の社会復帰を目的としてリハビリテーションにスポーツが活用されたことが起源になっています。
1948年に、ストーク・マンデビル競技大会が開催され、これがパラリンピックにつながっています。
1964年の東京パラリンピックでは、日本の選手たちは療養所から参加しています。
パラリンピックに出場している障害者を見ることは、地域で見かける障害者を見ることとかけ離れたものではありませんでした。
パラリンピックの選手を見ることが、障害者に対する見方を変えることに直結していたと思います。
1964年の東京パラリンピックは、出場する障害者を見てもらうことによって、一般的な障害者と社会との関係を改善する装置として機能していました。
【聞き手】
1964年の東京パラリンピックの報告書(国際身体障害者スポーツ競技会 東京パラリンピック大会報告書)の余禄に、当時の新聞論説がいくつか紹介されていました。
その中には、パラリンピックに出場した日本代表選手が外国人の選手の明るさに驚き、その明るさは、生活の安定や社会一般の理解があることと繋がっているという指摘もありました。
日本代表選手は、海外の選手の様子を見て、福祉施策や社会環境の違いを感じた人が多かったようです。
1964年の東京パラリンピックと、最近のパラリンピックは、どのような点が違うのでしょうか。
【橋本】
障害者白書をみると、現在、日本の障害者は960万人となります。
そのなかで、パラリンピックに出場できる人はどのくらいいるでしょうか。
2016年のリオ・パラリンピックで日本代表選手は132人です。
障害者の大半は高齢者です。
高齢で中途障害の方には、パラリンピックを目指すことはかなり難しいです。
先天性の肢体不自由児についても、参加できる競技は一部しかありません。
年齢的にも、障害の種別的にも、パラリンピックに出場できる障害者は、障害者のごく一部です。
また、近年、パラリンピックの競技性が高くなりました。
オリンピックと同じように、訓練をして鍛え上げたエリートアスリートが出場するようになっています。
体操の内村航平選手やフィギュアスケートの羽生結弦選手は、その競技で高いパフォーマンスを発揮できる優れた能力を持った人ですよね。
一般の人にとって、オリンピック選手は、雲の上の人じゃないですか。
パラリンピックの選手は、地域で生活している障害者の代表ではありますが、象徴だとは言えなくなっていると思います。
2020年の東京パラリンピックに向けて、メディアに障害者アスリートが登場することが増えたことは、一般の人の障害者アスリートに対する見方やイメージを変えることには繋がっているかもしれません。
しかし、障害者アスリートを見ることが、障害者全般に対する認識の変化につながるかどうかは疑問になります。
テレビや広告に起用されている障害者アスリートと、地域で身近に見かける障害者とが必ずしも重ならないからです。
例えば、オリンピックの陸上競技で金メダリストを獲得したウサイン・ボルト選手を見て、ジャマイカ人がどのような人かは分からないですよね。
特定の属性を持つ集団の中のスーパーマンに注目するだけでは、その集団の属性を知ることはできません。
イギリスでは2012年から16年にかけて障害者スポーツの強化費は増えましたが、障害者の生活環境は悪化をしているという調査結果もあります。
パラリンピックは、競技が高度化したことによって、果たすことができる役割が変わってきました。
一般の方の障害者に対する認識を変える装置として、昔と同じ効果が出るとは言えないと思います。
【聞き手】
障害者に関する教育については、橋本さんが監修されたテキストで、アイマスクをつけて視覚障害の体験をする学校の授業が、必ずしも視覚障害の理解につながらない面があることを指摘されていますね。
【橋本】
障害の疑似体験は、「障害があることは、こんなに大変なんだ」という意識をつくることにつながり、「大変だから、助けてあげましょう」という考え方につながります。
「なぜ、大変なのか」といえば、障害のない人と比べて「能力が低いから」という見方になります。
障害に原因を求める「障害の医学モデル」の考え方です。
パラリンピック関係の報道やPRを見ていると、「視覚障害があるので、聴覚を使う」など、「障害があるから、〇〇をする」という説明があります。
教育や報道は、本来、「障害の社会モデル」の見方につなげたいのですが、こうした表現では、障害そのものに注目する「障害の医学モデル」が強調されてしまうのです。
【聞き手】
障害そのものに注目すると、「視覚障害の方は、目が見えないから大変だ」「車いすの方は、足で歩いて移動ができないから大変だ」と見てしまいがちかもしれません。
実際は、大変かどうかは人それぞれで、何か困っている様子の人がいたら、その方が必要とする支援を考えることが大切ですね。
2020年に向けては、「障害の医学モデル」ではなく、「障害の社会モデル」の理解を拡げることになっていますが、現状はどうでしょうか。
【橋本】
パラリンピックを見ることや障害者スポーツの体験をすることが、一般の人の障害者の理解につながるという分かりやすいパッケージがあり、それを無条件で信じている人は多いと感じています。
障害に注目する「障害の医学モデル」で啓発されているものもあると思います。
2020年に向けてさまざまな施策や事業が動いており、その大きな流れの中にあるものを止めるのは難しいと思います。
そういう現状があるとしても、私自身は、2020年の東京パラリンピックをチャンスだと捉えています。
東京大会の開催が決定した2013年頃まで、「障害者スポーツの事業をしています」と言っても、話を聞いていただける人はほとんどいませんでした。
最近は、「講演に来てください」と言われるようになりました。
これほど障害者スポーツに興味や関心が集まるのは、これまでにないことです。
興味を持ってくれた人に、いち早く、「障害の社会モデル」を知ってもらえるように啓蒙することが大事です。
また、障害者福祉や、障害者スポーツについてもっと深く知りたいと思ってくれた人に学べる環境を準備していくことが必要だと考えています。
【聞き手】
一般のスポーツでは、オリンピックやプロ野球のように競技性の高いスポーツと、趣味や健康増進のためのスポーツがあります。
障害者スポーツは、もともとリハビリテーションの一環で始まりましたが、パラリンピックは競技性が高いスポーツになったというお話でした。
橋本さんが携わっているのは、障害者スポーツの中でも、競技性が高いものではなく、リハビリテーションのスポーツだと伺っています。どのような活動をされているのか。詳しく教えていただけますか。
【橋本】
リハビリテーションスポーツは、障害のある人の社会参加のツールとして使うスポーツで、医学的に行うものと、地域の活動として行うものがあります。
私は、地域でこれからスポーツをはじめる方向けの指導や、そういった指導を行うことができる人材の育成をしています。
障害のある方がスポーツをはじめる場合、動機づけができていることは少ないです。
障害があることで体を動かすことに自信がなかったり、仲間づくりに不安があったりします。
そういったなかで、医者や家族に勧められて、いやいや参加する方も少なくありません。
これからスポーツを始める方への指導というのは、そういった心理状況に配慮し、成功体験や仲間づくりを通して、継続参加を促すことから始めます。
【聞き手】
地域の活動の中で、スポーツを社会参加のツールとして使うというのは、どういうことですか。
【橋本】
「自分に何かができる」という感覚、自己有能感という指標があります。
何かできないことがあると、自己有能感が持てなくなります。
例えば、受傷して障害を負い、できないことがたくさんあると、そういう自分は価値がないと考えるようになります。
そうなると、本来は障害が原因でないことまで、障害を原因にしてしまうようになります。
「障害があるから、これができないんだ」と考えてしまうんです。
その状況を変えるのに効果的に活用できるツールが、スポーツです。
体が動かないためにいろいろなことができないと思っている方に、体を動かしていただいて、何かができると感じるもらうことが有効です。
もちろん、カラオケや手芸などでも同じような効果があるとは思いますけど、身体動作ができなくなることで失った自信は、身体動作で取り戻すのが一番効率が良いと思います。
地域のスポーツ活動では、受傷前とは違う新しい身体で、「できる」という感覚、自己有能感を持てる機会をつくります。
「これができたから、他のこともできるかもしれない」という動機づけが、復学や就労への意欲につながります。
地域でのスポーツの活動は、一人でなく、集団をつくりやすいので、自分を大切にしてくれる他者と出会い、他者受容感を持てる機会にもなります。
「何かをやってみたい」「達成してみたい」というものがあり、その目標に向かって立ち向かっていかなければならない時に、「あの時、あれができたから、今回もやってみたらできるかもしれない」と思えること。
そういう気持ちの核みたいなものを、どうやってつくるか。
地域のスポーツ活動を通して、障害のある方への心理的なアプローチに取り組んでいます。
【聞き手】
2020年に向けて、これから取り組みたいことはありますか。
【橋本】
私の活動は、2020年の東京パラリンピックの開催の有無に関係なく続けてきたものですので、基本的な活動の方向性はこれまでと変わりません。
障害者スポーツは、もともと社会参加のツールとして始まったものですので、その機能はしっかりと残していきたいです。
ただ、社会環境が変わり、パラリンピックの在り方は変わりました。
パラリンピックが果たせる役割も変わってきたと思います。
競技性の高いエリートスポーツだけではなく、社会参加のためのツールとしてのスポーツを普及していかなければなりません。
私にできるのは障害の社会モデルの理解促進と地域での社会参加促進のツールとしてのスポーツ普及です。
障害のある方が、その障害が原因で機会を制限される状況がまだまだあると思います。
そういう状況を減らしていくようなことを、1つでも積み重ねていきたいと思います。
個人的には、障害が原因で外出のきっかけがなく、孤立状態になっている方に、スポーツの活動が外出のきっかけになるようなことをしたいですね。【了】
橋本大佑さん/プロフィール
一般社団法人コ・イノベーション研究所代表理事。筑波大学で障害児教育を専攻、卒業後、ドイツに渡り、車いすスポーツを通した障害児・障害者への運動導入の指導法について学ぶ。ドイツ障害者スポーツ連盟公認リハビリテーションスポーツ指導者B(車いすスポーツ)資格を取得している。
2009年に帰国後、スポーツを通じた障害者の社会参加を促進する活動に取り組み、各地で研修会の企画・運営・講師などを行っている。2016年より現職。
聞き手/河原レイカ(パラスポ!代表)
【関連情報】
一般社団法人コ・イノベーション研究所
http://www.coil.or.jp/
内閣官房 東京オリンピック競技大会・パラリンピック競技大会推進本部事務局委託事業
平成28年度オリンピック・パラリンピック基本方針推進調査(ユニバーサルデザインの社会づくりに向けた調査)報告書
- 投稿タグ
- 企画特集